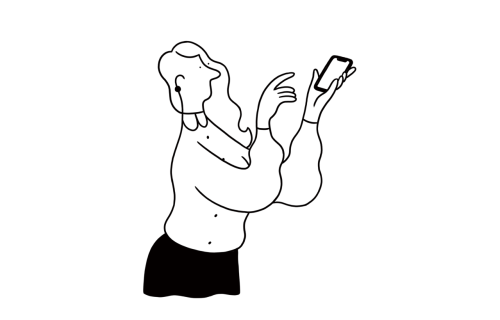
ゼロバンク・デザインファクトリー(※)の長島です。フロントエンドエンジニアとして働いています。
※ゼロバンク・デザインファクトリーは、ふくおかフィナンシャルグループの一員で、みんなの銀行のバンキングシステムを開発しています。
みんなの銀行では、“アクセシビリティ”を「より多くのお客さまが、より多くの利用環境から、より多くの場面や状況で情報やサービスにアクセスできること」と定義し、改善に取組んでいます。主にスクリーンリーダー(音声読み上げソフト)における挙動改善を目的とし、2023年1月から定期的に機能改善のリリースを続けています。
アクセシビリティをテーマにお届けする本連載では、視覚障害のあるお客さまにご協力いただいたユーザーインタビューとユーザビリティテストについて、実施前の状況から実施後の変化までを、フロントエンドエンジニアのキム・ジョンア、デザイナーの鶴大輝とともに振り返りながら、それぞれの立場で得た気づきと学びをお話ししてきました。
最終回[後編]となる今回は、インタビューを通じて見えてきた「デジタルバンクが担うべき責任と可能性」について語り合います。
スマホの中の銀行「デジタルバンク」。それ自体が持つ、アクセシビリティの可能性
鶴 ここまでお二人の話を聞いていて、そもそも「デジタルバンク」というサービスのあり方そのものに、アクセシビリティの観点で優れている部分があったと改めて気づきました。
インタビューでお客さまが教えてくださったお金・銀行に関連する問題は、大きく2つありました。1つ目は「視覚障害のため一人での外出が難しく、用事はできるだけ家で完結させたい」ということ。2つ目が「支払い時に小銭やお札を確認するのに、手で触ったり、見える人に確認してもらったりする必要がある」という点です。
みんなの銀行なら、デビットカードでのネット決済や振込はスマホひとつで家からできますし、現金に触れる必要もありません。まさにこの2つの問題を解決できる、というお話でした。
デジタルバンクという存在自体が、物理的な制約を取り払うアクセスしやすい仕組みなんですよね。だからこそ、私たちがその上で提供する顧客体験を突き詰めれば、自然とアクセシビリティとユーザビリティを両立できる部分があるのだと、再認識しました。
長島 少し技術的な話になりますが、みんなの銀行はスマホでの利用に特化しているため、画面のデザインが「下から上に積み上がる」というシンプルな構造になっています。
これがもしパソコンのWebブラウザだと、画面の幅に応じて表示レイアウトが変わるなど、考慮すべきデザインのパターンが複雑になりがちです。
私たちは「モバイル専業」という制約が良い方向に働き、基本的には画面の各要素に「上から順番に名前を付ける」「それがボタンなのかテキストなのか役割を定義する」「エラーでボタンが押せないなどの状態を伝える」という3点を丁寧に行えば、スクリーンリーダーで操作可能になります。これは開発のしやすさにもつながっています。
さらに視点を広げると、「デジタルバンク」は「金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン)」という考え方にも貢献できると感じています。
世の中には、さまざまな理由で金融サービスを十分に受けられない方々がいます。例えば、銀行口座を持ちたくても持てない「unbanked(アンバンクド)」と呼ばれる人々や、障害や居住地の問題で銀行の店舗に行けない方々です。
最低限の通信環境とスマホさえあれば、誰もが金融サービスを受けられる。みんなの銀行のビジネスモデルには、私たち自身もまだ気づいていない大きなポテンシャルが眠っているのだと思います。
当事者の“リアル”に触れて。開発者たちが得た一番の学び
長島 鶴さんのご紹介でお客さまにご協力をいただき、インタビューが実現しました。アプリに関するご意見だけでなく、普段の生活でどのように金融サービスを利用されているか、幅広くお話を伺いました。
お二人にお聞きしたいのですが、インタビューの前後でアクセシビリティや視覚に障害のある方々に対するイメージは変わりましたか?
キム やはり一番の驚きは、スクリーンリーダーの操作でした。自分がテストで操作する際は、少しでも意図通りに動かなければ「バグだ」と捉えていました。
でも、実際にお客さまが操作する様子を拝見すると、経験から「このあたりにボタンがあるだろう」「こう操作すれば先に進めるはず」と、ある程度予測しながら使われていることが分かりました。
この発見から、細かな修正を積み重ねることよりも、ユーザー体験を根本的に損なっている、より大きな課題から解決すべきだと考えるようになりました。
長島 よく分かります。実際に使われている場面を拝見したことで、「この問題は致命的か、それともまだ許容範囲か」といった優先順位づけの解像度が上がったように感じます。
もちろん、この感覚も「決めつけ」につながる危険性があるので慎重になるべきですが、何も見ずに想像するのと、一度でも拝見した上で仮説を立てるのは、全く精度が異なりますよね。
キム 本当にそうだと思います。
長島 とある先進的な企業では、開発チームにスクリーンリーダーを日常的に使う方が在籍しているそうです。開発の初期段階から当事者の意見を取り入れられるのは理想的な環境ですよね。
私たちはまだその段階には至っていませんが、まずは今回のように直接お話をお伺いし、リアルな利用シーンを見せていただくことが、大きな一歩になるのだと実感しました。鶴さんはいかがでしたか?
鶴 視覚に障害のある方は、私が想像していた以上に、ご自身の力で様々なことをこなされていて、スマホも私たち視覚に障害のない者と変わらないレベルで使いこなされていることに、純粋に驚きました。正直に言うと、「これは難しいのではないか」と私たちが勝手に限界を決めつけていた部分もあり、深く反省しています。
また、個人的には「アプリの一部分を少し変えたところで、大きな変化にはつながらないのではないか」という思い込みもありました。
しかし、お話を聞いて、小さな改善の積み重ねが、日々の生活を大きく変えるほどのインパクトを持つ可能性があるのだと痛感しました。同時に、私たちが配慮を怠れば、ほんの少しの変更が著しい使いにくさにつながり、利用を諦められてしまう恐怖も感じました。
長島 まさに、希望でもあると同時に、大きな責任が伴うということですね。私たちが当たり前だと思う品質を一つひとつ積み重ねていく。それによって「使いやすくなった」と言っていただける可能性がある一方で、そこを怠ると先に進めなくなるような致命的な不具合を生んでしまう。
今回、お話を聞かせてくださったお客さまがご自身でウェブサイトを作るぐらいITにとても詳しい方だったことは、私たちにとって幸運でした。もし、そこまでスクリーンリーダーに慣れていない方だったら、途中で諦めてしまったかもしれません。
やはり、鶴さんがおっしゃるように、課題の本質を見極め、当たり前の品質を地道に積み重ね、その効果を検証していく。アクセシビリティに限らず、サービス品質の向上において、このサイクルがいかに重要かをと改めて感じました。
私たちの「次の一歩」
長島 今回のインタビューを通じて、私たちは数多くの課題と改善のヒントを得ることができました。今回ご協力いただいた方からの貴重なご意見は、すでに開発チーム内で共有し、今後の改善項目としてリストアップしています。
例えば、アプリだけではなくFAQサイトを含めた部署横断の改善が必要であると分かったことも、その一つです。FAQサイトを作成するグループとデジタル庁が配布している「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」(https://www.digital.go.jp/resources/introduction-to-web-accessibility-guidebook)の読み合わせを行ったり、アプリエンジニア・FAQサイト担当・デザイナーのチャットグループを作成し改善に向けた情報交換・タスク調整などを行っています。
鶴 デザイン面でも、すぐに着手できることから見直しを始めています。今回の学びを一時的なものにせず、今後のプロダクト開発全体のプロセスに組み込んでいくことが重要だと考えています。
おわりに:「みんな」の銀行であるために。これからの挑戦
[前編][中編][後編]の全3回にわたってお届けしたユーザーインタビューの振り返り、いかがでしたでしょうか。
記事の中でも触れたように、アクセシビリティはスクリーンリーダーだけの問題ではありません。その名が示す通り「みんな」が、みんなの銀行を当たり前に使える状態を目指して、私たちはこれからも、より多様な視点からアクセシビリティの改善を続けていきます。
そして、その改善を本当に意味のあるものにするためには、障害の当事者の皆さまのリアルな声が不可欠です。
もし、私たちの取組みにご共感いただき、より良いサービスを作るために「自分の声を話してもいいよ」という方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡をいただけますと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※この記事はオウンドメディア『みんなの銀行 公式note』からの転載です。
(執筆者: みんなの銀行)
