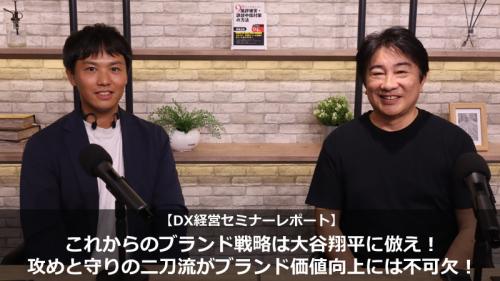
デジタルシフトウェーブは2025年8月19日、定例セミナーを開催しました。今回のテーマは「ブランドは“攻め”と“守り”で伸ばす~ブランド価値を高める二刀流戦略~」。自社や自社製品・サービスのブランド価値を引き上げる方法を、攻めの戦略と守りの戦略の両面から考察しました。
自社や自社製品・サービスの価値を訴求し、競合との差異化を図るブランド戦略。多くの企業がユーザーからの共感を獲得すべく、価値向上に向けたさまざまな施策を打ち出しています。中でも近年はSNSを駆使した施策が増加。価値や魅力をSNS経由で頻繁に発信するケースが目立ちつつあります。
しかし、一歩間違えば悪評が広がり、ブランドの価値を大きく棄損しかねません。こうしたデジタルリスクを懸念し、積極的な施策に打って出られない企業も決して少なくありません。
そこで今回のセミナーでは、これからのブランド価値向上施策を考察。とりわけ、悪評などの風評被害を防ぐ「守りの戦略」と、価値を効果的に高める「攻めの戦略」の2軸でブランド価値を引き上げる方法について紹介しました。企業の価値向上施策を支援するブランドクラウド 代表取締役社長の叶野雄与氏をゲストに迎え、攻めと守りの「二刀流」によるブランド戦略を効率よく進める方法を解説しました。
デジタル時代におけるブランド価値の変容と「守り」の重要性
セミナーでは叶野氏がブランドクラウドの事業を説明するとともに、ブランド価値について改めて解説。ブランドを理解しやすくするため、コカ・コーラとペプシの味覚テストの事例について触れました。「ある調査では、ラベルを隠した状態ではペプシが好まれた。一方、ラベルがある状態ではコカ・コーラが圧倒的に選ばれる傾向があった。つまり、味の本質を分かるユーザーはごくわずかに過ぎない。多くのユーザーはイメージや情報をもとに商材やサービスの良さを判断してしまう」(叶野氏)と指摘。ブランドのイメージや情報が消費者の購買行動に大きな影響を与えることを強調しました。

一方、悪い評判がブランドに与える影響についても言及します。叶野氏は、「情報過多の現代では、企業が発信する良い情報だけではなく、悪い情報にも注目が集まりがちだ。オックスフォード大学が実施した研究結果によると、悪評は良い評判の3.7倍の速度で拡散するという。しかも良い評判より3倍もユーザーに記憶されるという。企業が認知拡大に向けて多大なマーケティング施策を展開しても、ネガティブな評判が瞬時に拡散されてしまう。こうした悪評を広げないための対策に目を向けるのも重要なブランド戦略である」と強調しました。さらに、これからのブランド戦略をMLB大谷翔平選手で例示。「大谷選手のように、打つと投げるを二刀流で成し遂げるように、ブランド戦略も攻めだけではなく守りもしっかりこなさなければならない。良い情報を広げる攻めの対策と、ネガティブ情報を発見しにくくする守りの対策をバランスよく実施することが、これから求められるブランド戦略である」(叶野氏)と述べました。
攻めの戦略:ブランドリフティングで認知度と信用性を高める
では、「攻め」と「守り」をどのように効率よく実施すればよいのか。セミナーでは叶野氏が代表を務めるブランドクラウドのソリューションを使った解決策も紹介。「ブランドリフティング」は、「攻め」の戦略推進を支援するソリューション。オンラインかオフラインを問わず、多様なプラットフォーム(PR TIMES、NewsPicks、Yahoo!ニュース、テレビ広告、ラジオ、看板広告、タクシー広告など)を活用して情報を発信し、PDCAサイクルを回しながらブランディング施策を管理します。発信する情報がない状態からインパクトを作る「0→1」フェーズから、インパクトを広げて拡散する「1→100」フェーズまで幅広く支援できるのが特徴です。
ユニークな技術を採用するのも特徴です。「ブランドリフティング」では、検索エンジンの「サジェスト」(検索予測)にポジティブな情報を認識させる機能を装備。例えば、「環境保全企業」と調べた際に「ブランドクラウドおすすめ」と検索予測に情報を追加できるといいます。「通常の広告施策と異なり、信用性のある認知を獲得できるのがブランドリフティングの強みである」(叶野氏)と強調します。
守りの戦略:風評被害クラウドでデジタルリスクから企業を守る
一方、ネガティブな情報を拡散させない守りの戦略をどう考えるべきか。ブランドクラウドでは「風評被害クラウド」と呼ぶ守り用のソリューションも用意。企業のネガティブな情報を一般ユーザーに発見しにくくできるといいます。
具体的に3つの「R」に紐づく施策を支援します。1つは「 IR(Investor Relations)対策」。Yahoo!ファイナンスやみんかぶなどに書かれた情報が株価に影響を与えるケースに対応し、社会貢献活動なども適切にユーザーに届けられるようにします。
2つ目は「BR(Brand Relations / Public Relations)対策」。ユーザーが検索した際にネガティブ情報に辿りついてしまい、購買を躊躇したり競合に流れたりするケースを防ぎます。叶野氏は「ユーザーは興味を持った商品をSNSや検索エンジンで調べる。その時の着地がネガティブだと離脱したり競合他社に流れたりしてしまう。せっかく投じた広告費の費用対効果も悪くなりかねない。こうしたリスク対策が企業にはより求められるようになる」と指摘しました。
3つ目は「HR(Human Resources)対策」。これは、転職サイトの口コミやネット上の評判が内定辞退や採用コスト悪化に繋がる深刻な課題に対し、対策を講じます。退職者の不満が誇張されて書かれいるなどの場合、こうしたレビューや口コミサイトの点数改善などを実施し、良い評判の投稿を増やすことで優秀な人材を集めやすくします。
こうした対策を効率化できるのが「風評被害クラウド」だと叶野氏が続けます。具体的には、「リスクマネジメントコンサルティング」や「デジタルタトゥー対策」などのサービスを用意し、対策を施せるようにします。
「リスクマネジメントコンサルティング」は、ソーシャルリスニングで収集した情報を分析し、企業の本質的な改善に繋がる環境作りをサポートします。ユーザーが特定のキーワードを調べている前後の興味関心や競合サービスを分析し、転職サイトのネガティブ口コミの原因と解決策を企業と伴走しながら進めます。
「デジタルタトゥー対策」は、会社名やプロダクト名、社長名で検索した際に、検索エンジンのサジェストに「激ヌル」や「ブラック」といったネガティブワードが表示されるのを防ぎます。正しい情報の関連性を高めることでネガティブワードをサジェスト枠から追い出すようにします。さらに、リスクサイトやネガティブサイトの情報を相対的に押し下げる「逆SEO」のような手法を駆使し、悪い評判を見えにくくするといいます。「ネガティブ情報が見られなくなった度合いを定量的に評価する当社の仕組みを使って調べたところ、デジタルタトゥー対策の成功率は94%を誇る」(叶野氏)と具体的な効果も例示します。
さらに「風評被害クラウド」では、最新のデジタルリスクにも対応します。例えば、多店舗展開する企業の自動生成アカウントにおける口コミや個人情報露出問題に対応し、削除や正しい情報発信で口コミ対策を実施します。「AIオーバービュー」と呼ぶ機能を使えば、Google検索結果の最上部に表示されるAI要約に、企業にとって不利な情報が載らないような対策も講じることが可能です。「AIオーバービューにより、不利な情報をもとにサイトを訪れるユーザーが35%減少したデータもある。その影響力は無視できない」(叶野氏)と強調します。その他、匿名掲示板などの誤情報や不正確な情報に対し、削除依頼や修正交渉を進めたり、AIが顧客とのメールのやり取りを監視し、危険性の高いやり取りを自動検知したりすることもできうるといいます。
「二刀流戦略」を成功させるための実践的視点
セミナーの後半では、実践的なブランディング戦略について、モデレータを務めた鈴木氏と叶野氏が対談しました。叶野氏は近年のブランド戦略を支えるSNS戦略について言及。「SNSは強力な武器となる一方、一歩間違えれば諸刃の剣となる。情報過多の現在では何が正しい情報か分からないという課題が顕在化している。こうしたユーザーが情報を取捨選択するリテラシー教育の重要性が増しつつある」(叶野氏)と考察しました。
一方、SNSのリスク管理まで手が及ばないという企業に対し、「最近は企業のリスク管理部の業務を請け負うBPOが登場している。GoogleだけではなくBingやSNS(Instagram、TikTokなど)、監視対象も広がりつつある。こうした業務をアウトソースするのも一案である」(叶野氏)と述べました。

もっとも、「何から取り組めばよいのか分からない」という企業も少なくありません。叶野氏はこうした企業に対して、「まずは現状把握から進めるべきである。ブランドクラウドでは無料のリスク調査レポートを提供している。会社名、商品名、商標、社長名などで検索した際に、現在どこにどのようなリスクがあるのかを、Google、Yahoo!、Bing、X(旧Twitter)ごとに調査、分析してリスクを可視化する。これにより、リスク対策を優先順位付けし、企業の状況に応じた対策を施せるようにする」といいます。無料の調査レポートは早ければ数日で対応可能で、マーケティングデータとしても有用だといいます。
叶野氏は最後に、リスク対策は事前の対策が重要だと強調しました。「特に年商10億円以上、社員100人超の企業や、上場を目指す企業、新商品・新サービスを発表する前は、銀行の融資審査や上場審査、テレビ出演の可否判断などにおいてWeb上のリスク状況を調べられる。こうした対策を事前に実施するだけでもリスクを十分回避できる。とりわけ日本人は有名になると叩かれやすい国民性を持っている。少し目立つ、もしくは目立とうかなというときの前にしっかり実施しておくのが望ましい」と、予防的対策の重要性も訴えました。
当日のセミナー動画は、DXマガジン会員様限定コンテンツです。
ご登録がまだの方は、今すぐ会員登録して動画をチェック!
