
KABETORI画面(AIが日本語の日報形式へリライト)
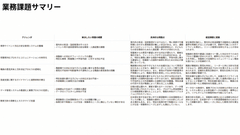
週次・月次のダッシュボード例

開発者ー余氏
前編ではKABETORI誕生の背景と、余氏が日本語教育とソフトウェア開発を掛け合わせるに至ったキャリアの軌跡をたどりました。後編となる本記事では、アプリに込めた設計思想をさらに掘り下げ、翻訳を超えて現場の課題を可視化する仕組みと、データ活用が切り拓く“定着支援”の未来像に焦点を当てます。
■1. なぜ“翻訳”にこだわるのかー真の目的は課題発見と生産性向上
KABETORIは一見すると多言語翻訳ツールのようですが、本質は現場の摩擦を減らし、生産性を上げるコミュニケーション基盤をつくることにあります。
たとえばベトナム人スタッフが十分なクオリティの業務を行えていないとして、原因究明が必要です。しかし「日本語での指示が理解できていないのか」「母語/英語での指示なら理解できるのか」「業務フローが理解できていないのか」など様々な原因が考えられ、どれが原因なのかを探るのにも、コミュニケーションが不可欠です。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/489271/LL_img_489271_1.png
KABETORI画面(AIが日本語の日報形式へリライト)
KABETORIでは母語で入力するだけでAIが日本語の日報形式へリライト。原文・直訳・リライト文を同時保存するため、意思疎通と記録作成が一度で完了します。翻訳はゴールではなく、対話を可視化し課題を抽出するための入口―これが開発思想の出発点です。
■2. 三層保存がもたらす“本音”の可視化
アプリには以下3つのデータが蓄積されていきます。
1. 母語の原文
2. 機械的な直訳
3. 丁寧な日本語に書き換えた日報文
週次・月次のダッシュボードでは、母語表現に潜むストレス語やネガティブ形容詞などから、モチベーション課題をAIが自動抽出します。それだけではなく、業務理解やコミュニケーションなどの業務効率化における課題も分析し、組織課題をデータ化します。
画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/489271/LL_img_489271_2.gif
週次・月次のダッシュボード例
■3. 文化の壁を乗り越えるAIリライト
従来型の機械翻訳は単語を置き換えるだけでしたが、KABETORIのAIは文脈と職場文化を踏まえて“書き換える”ことに重きを置きます。
例えば、小学校で日記を書かせると、子どもたちは頭の中に「算数いやだ」「もっと遊びたい」など具体的なモヤモヤを抱えているのに、語彙や作文力が足りず「つまらなかったです」程度しか書けないことがありますよね。KABETORIのAIリライトは、まさにその“書けない”部分を埋める担任の先生のような存在です。
《頭の中の感情(思っているけど書けない)を職場がすぐに動ける課題の形に変換する》
この“橋渡し”こそがAI翻訳の真価。言語能力に依存せず、本質的な課題だけを抽出して共有できるため、管理者は即座にアクションを起こし、生産性向上や問題解決につなげられるのです。
■4. 翻訳精度より“誤解を残さない”設計
誤訳リスクをゼロにできない前提で、KABETORIは
● 三層表示による相互チェック
● 改ざん不可のログ保存
● クリック式4段階評価で書き漏れ防止
という安全網を用意しました。万一翻訳に揺らぎがあっても原文と直訳が残るため、原因を遡りやすく現場の信頼を守れる仕組みです。
■5. データ基盤一元化が拓く次のステージ
日報データは同社サービス<MICHISUJI>へリアルタイム連携。CSV連携や二重入力とは無縁で、“SaaS疲れ”を起こさないエコシステムを実現しています。
余氏はこの統合基盤を活かし、現場言語×AIで自動生成するビジネス日本語教材を構想中。日報に現れた表現をAIが抽出し、「次回はこのフレーズを使ってみよう」と教える―自律学習サイクルが動き始めています。
■6. 教育視点で描く“定着支援”のゴール
コミュニケーション改善は手段であり、究極の目的は外国人就労者が安心してキャリアを伸ばせる「定着」にあります。
1. 母語で本音を吐き出し
2. AIが日本語へ変換して共有し
3. 管理者が迅速に対応し
4. データが学習素材として還流する
―この循環が回れば、企業は離職・失踪リスクを抑え、働き手は「居心地の良い日本」を実感できます。余氏はこう締めくくります。
「KABETORIは翻訳アプリではなく、多文化チームを“育成する”コミュニケーションプラットフォームです。母語も日本語も活きる場を設計し、そこから現場の課題を拾い上げる――それが私たちが描く次世代の定着支援モデルなのです。」
翻訳はゴールではありません。AIと日本語教育の融合で、現場の“声”を課題に変え、未来の働き方を変えていく――KABETORIが示す挑戦は、今まさに動き始めています。
画像3: https://www.atpress.ne.jp/releases/489271/LL_img_489271_3.png
開発者ー余氏
【会社概要】
商号 : 株式会社アップカル
代表者 : 杉山 満軌
所在地 : 〒914-0264 福井県敦賀市杉津4-7-1
設立 : 2023年12月
事業内容: (1)外国人人材採用・定着・生産性向上のサポート
(2)上記統合システム・アプリケーションの開発及び提供
URL : https://upcul.co.jp/
