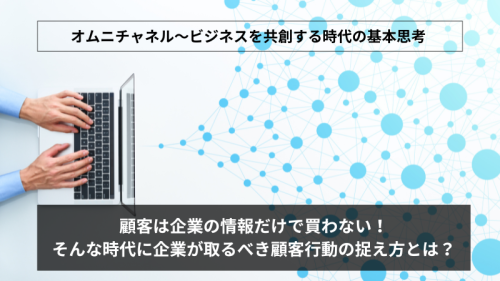
オムニチャネルとは、顧客を起点に考えるアプローチであり、その実現にはマーケティングの視点が不可欠です。しかし現実には、「マーケティング=販売促進」と誤解されているケースも多く見られます。前回は、マーケティングの本質は「顧客理解」にあるという点をお伝えしました。今回は、その「顧客理解」を実際にどのように深めていくのかについて解説します。顧客の行動を“見える化”する方法、そしてマーケティング施策を考える上で特に重要となる「情報接点」と「購入接点」について整理していきます。【オムニチャネル~ビジネスを共創する時代の基本思考#11】
自社の顧客を見える化する
売上や利益の構造を分解、把握することも「顧客理解」には必要です。とりわけ「顧客」「商品」「販売チャネル店舗・EC)」という3つの軸に分けて分析することで、売上や利益が増減する要因を把握できるようになります。例えば「顧客」なら、会員と非会員に分類したり、新規か既存でセグメントしたりします。年間の購入頻度、購入金額、平均単価などの指標でグルーピングするのも有効です。
分類した顧客グループがどんな商品を購入しているのか、どのくらいの価格帯の商品を高頻度で購入しているのかも探ります。同様にと販売チャネル(店舗・EC)ごとのの利用状況や重複率なども探ります。これにより、特定の顧客層の行動パターンや関心、志向を可視化できるようになります。顧客を細かく分類して「顧客理解」を深めることで、特定の顧客層向けのマーケティング施策も立案することができます。
もっとも顧客を理解するヒントは、定量的なデータ分析だけにとどまりません。店舗を展開する小売事業者なら、店舗の店長や現場のスタッフの感覚を把握するプロセスも有効です。例えば、「データでは女性の利用率が高いが、男性の利用率は決して少なくないと感じる。とりわけ夫婦や子供連れで来店する男性が目立つ」といった現場のインサイトを得られれば大成功です。データでは気づきにくい現場の状況は、マーケティング施策の成功率を大きく引き上げます。
情報接点と販売接点、分けていますか?
マーケティング施策において、「情報接点」と「購入接点」の設計が重要になっています。近年、顧客との接点が「情報」と「購入」に分離されてきています。2000年頃までは、商品やサービスの・内容を知るには、店舗へ足を運び、実物を見て、店員の説明を聞くのが当たり前でした。つまり、「情報接点」と「購入接点」は、どちらも同じ店舗にあり、一体化していたのです。
しかし、2003年頃からインターネット環境が変化します。家庭のネット接続が従量課金制から定額制に移行し、かつ高速化が進んだことで、誰もが日常的にネットを利用するようになりました。それに伴い、実物を見に行かなくても、ネット検索で多くの情報を得ることが可能になったのです。
さらに、mixiやブログといったサービスが普及すると、企業だけでなく、一般の消費者や生活者もネット上で情報を発信できるようになります。そして、企業が発信する公式情報と同等か、それ以上にリアルな消費者の声が注目されるようになってきました。
2014年頃からはスマートフォンが急速に普及し、自宅や職場に限らず、外出先などあらゆる場所で、必要なときに必要な情報を即座に検索・取得できる環境が整います。このように生活環境と情報行動が変化する中で、商品購入時の行動も大きく変わりました。現在では、「情報接点」と「購入接点」は明確に分けて活用されるようり、ECサイト上で商品を閲覧してもすぐには購入せず、一度店頭で実物を確認し、その後SNSで他の購入者のレビューをチェックしてからオンラインで注文する、という行動パターンも一般的になっています。
特に「情報接点」においては、企業発信の情報よりも、実際に商品を使った一般消費者のリアルな声の方が、購入判断に大きな影響を与えるようになりました。そのため、企業も自社の情報発信に「お客様の声」を取り入れたり、SNS上でユーザーとつながって情報を拡散したりするなど、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の重要性を強く認識し始めています。
一方「購入接点」においては、従来の店舗や自社EC・モールECに加えて、SNSを通じた購入ルートが増えています。たとえば東南アジアでは、自社サイトへの集客が難しいため、最初からShopeeやLazadaといったモール型ECに出店し、自社SNSからそこへ誘導する「SNSコマース」が主流です。日本でも、いよいよTikTokコマースが本格始動し、その動向が注目されています。
このように、現在は店舗でもECでも、顧客の購買や行動履歴がデータとして取得できるようになっています。だからこそ、顧客視点に立った「情報接点」と「購入接点」の設計が求められ、情報と購入をシームレスにつなぐ「オムニチャネル化」のさらなる推進が重要になっているのです。

逸見光次郎
CaTラボ 代表取締役
日本オムニチャネル協会 理事
1994年に三省堂書店に入社し、神田本店や成田空港店などで勤務。1999年にソフトバンクに移り、イーショッピングブックスの立ち上げ(現:セブンネットショッピング)。2006年にはアマゾンジャパンに入社し、ブックスのマーチャンダイザーを務める。2007年にイオンに入社し、ネットスーパー事業の立ち上げ後、デジタルビジネス事業戦略担当となる。2011年、キタムラに入社し、執行役員EC事業部長を経て、2017年にオムニチャネルコンサルタントとして独立。現在はプリズマティクスアドバイザーやデジタルシフトウェーブのスペシャリストパートナーなどを務める。
日本オムニチャネル協会
https://omniassociation.com/
