イギリスのケント大学(University of Kent)を中心とする研究チームは、フェイクニュースや陰謀論などに対抗するための「心のワクチン(認知ワクチン)」を開発したと発表。
実験では、「認知ワクチン」として短いメッセージを読むだけで、自分の考えに過信せずに多角的な視点を持てるようになり、その結果としてフェイクニュースや陰謀論にだまされにくくなれることが明らかになったのです。
なぜ、短い文章を読むだけで、フェイクに対する抵抗力が高まるのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年8月20日に『Journal of Experimental Social Psychology』にて発表されました。
目次
- なぜ人はデマや陰謀論を信じてしまうのか?
- 認知ワクチンはフェイクニュースに耐性を与える
- 認知ワクチンの意外な副作用
なぜ人はデマや陰謀論を信じてしまうのか?

私たちはインターネットやSNSを通じて、毎日膨大な情報に触れています。
しかしその情報の中には、意図的に作られた嘘やデマ、いわゆる「フェイクニュース」も数多く紛れ込んでいます。
こうした偽情報(ミスインフォメーション)は、社会に混乱をもたらす深刻な問題です。
たとえば、最近よく話題になった陰謀論の一つに、「5G電波塔は人間に害を与える」という根拠のない噂があります。
このデマを信じた人々が実際に5G基地局に放火をしてしまうという事件さえ起きています。
また、新型コロナウイルスのワクチンについても、「接種すると危険だ」といった誤った情報が広まり、ワクチン接種を避ける人が増えるという社会問題にもなりました。
こうしたフェイクニュースや陰謀論は、ただ単に「情報の嘘」だけが原因ではありません。
実は、人間の心理的な「考え方のクセ(認知バイアス)」も深く関わっています。
私たちの頭は、知らず知らずのうちに自分に都合よく情報を集めたり、物事を偏って解釈したりしてしまいます。
あえて言うなら、頭の中に「偏った眼鏡」をかけてしまっているようなものです。
この「偏った眼鏡」の代表的な例が、「確証バイアス」と呼ばれるものです。
確証バイアスとは、自分の意見を支持する情報ばかりを探し、反対の意見や都合の悪い情報を無視してしまう傾向のことを指します。
また、私たちはしばしば自分が何かを理解していると思い込みますが、実際にはよく理解できていないこともあります。
これを「理解の錯覚」と言います。
このような「考え方のクセ」が強い人ほど、フェイクニュースや陰謀論に簡単にだまされやすくなることが分かっています。
では、どうしたらこうしたクセを修正できるのでしょうか?
最近、心理学の研究者が注目しているのが、「積極的開放思考(Actively Open-minded Thinking, AOT)」という考え方です。
積極的開放思考(AOT)とは、自分の考えに絶対的な自信を持たず、むしろ「自分は間違っているかもしれない」と謙虚になって、他の意見や新たな証拠にも積極的に目を向けようとする態度のことを指します。
これまでの研究によると、このAOTのスコア(AOTのレベルを測った数値)が高い人ほど、偽情報に騙されにくいことが分かっています。
逆に、AOTスコアが低い人ほど陰謀論を簡単に信じてしまう傾向も報告されています。
そこで今回の研究チームは、AOTを高めることができれば、結果としてフェイクニュースや陰謀論に騙されにくくなるのではないかと考えました。
つまり、ニュースや情報の真偽を一つずつ検証していくのではなく、私たちの「考え方そのもの」を鍛えて、フェイクに騙されにくい頭を作ろうという試みです。
こうした考え方のクセを修正する試みは「認知ワクチン」とも呼ばれていて、医学で病気の予防接種を受けるように、事前に心の抵抗力をつける方法として期待されています。
今回の研究は、この新しい心理学的なアプローチが本当に効果的かどうかを調べることを目的としています。
認知ワクチンはフェイクニュースに耐性を与える
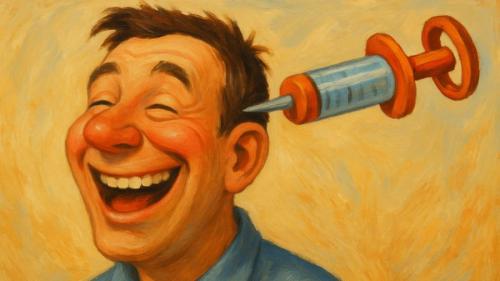
今回の研究チームは、認知ワクチンが本当に効果があるのかを確かめるため、Study 1 と Study 2 の2つが行われ、それぞれインターネットを通じて参加者を募集しました。
参加者は無作為に2つのグループに分けられ、片方のグループは「認知ワクチン」を受け取るグループで、もう一方はワクチンを受け取らない対照グループです。
(※ただしstudy1のワクチンを受け取らないグループは何もしない、study2のワクチンを受け取らないグループは簡単な作業をするという違いがありました。)
与えられる「認知ワクチン」には、自分の考え方や情報の見方を注意深くするための、人が陥りやすい次のような5つの考え方の落とし穴を警告したり避けるようにする内容が含まれています。
ここでいう5つの落とし穴とは
- 自分の考えに自信を持ちすぎる(過信)。
- 他の可能性を考えない(視野の狭さ)。
- 理解していないことに気づかず、「分かったつもり」になる。
- 自分に都合のよい情報ばかりを集める。
- 不利な情報さえも、自分に都合よく解釈する。
というものです。
たとえば「80%の人が『自分の意見を変える前には、賛成・反対の両方の意見をもっとしっかり確認したほうがいい』と答えた」や「ネットには人の思い込みを利用して情報を操ろうとする人がいる」などです。
さらに、これらの落とし穴に気をつけることで、「すべての情報を疑う必要はないけれど、どの情報を誰から信じるかを見極めることが重要だ」と強調されました。
そして最後は「自分が考えたことを何でも鵜呑みにしないように」とアドバイスして締めくくられ「認知ワクチン」の摂取が完了します。
一方で、ワクチンを受け取らない対照グループは、こうした特別なメッセージを受けずに調査を行いました。
このような実験を通じて、「認知ワクチン」によって本当に人々の考え方が変わるのかを調べました。
実験結果は、研究者たちの予想を裏付けるものでした。
ワクチンのメッセージを読んだグループでは、直後に行った調査で、他人の意見にも柔軟に耳を傾けようとする「積極的開放思考(AOT)」というスコアが明らかに上昇しました。
これはつまり、参加者たちが「自分の意見が本当に正しいのか、もう少し冷静に考えてみよう」と考えるようになったことを意味しています。
さらに、情報の見分け方についても良い結果が出ました。
具体的には、Study 2では偽物と本物のニュースを見分ける力が直接的に向上しました。
Study 1でもAOTが上がることで間接的にニュースを見分ける力が高まりました。
陰謀論を信じる度合いについても、ワクチンを受け取ったグループは低くなりました。
例えば、「政府が極秘の陰謀を進めている」という主張を信じる人が少なくなったのです。
Study 1ではこの効果が直接的に表れ、Study 2ではAOTが上がった結果として間接的に表れました。
SNSなどで情報を拡散したいかどうかについての意識も変化しました。
Study 1では、偽ニュースをSNSで「拡散したい」という意図が減りました。
別の分析では、本当のニュースをシェアしたい気持ちさえも少し減ったという結果がありました。
(※この違いはStudy 2で使われた「無関係な課題」が、単に何もしないstudy1の場合よりも参加者の集中力や意識を一定に保つ役割を果たした可能性があります。このため、ワクチン文の効果がStudy 2の方でよりはっきりと現れたのかもしれません。)
これは、情報を広める前に「ちょっと待って、本当に正しい情報かな?」と慎重に考える姿勢が強まったためだと考えられます。
また、CRT(認知反射テスト)という、よく考えれば簡単に解けるクイズのスコアもわずかに上がりましたが、実際に結果(フェイクを見抜く力や陰謀論を信じにくくなること)と一貫して結びついていたのはAOTの変化だけでした。
つまり、単に頭を回転させて考えるだけでなく、「もしかすると自分は間違っているかもしれない」という謙虚な態度が重要で、これこそがフェイク情報に強くなるための鍵なのだと分かったのです。
認知ワクチンの意外な副作用

今回の研究は、私たちがフェイクニュースや陰謀論といった誤った情報にだまされにくくなるために、「考え方そのものを変える」新しい方法を提案したものです。
私たちはふだん、何かのニュースや情報を見たり聞いたりするとき、「これは本当だろうか?」と一度立ち止まるよりも、「なるほど、そうなのか!」とすぐに納得してしまいがちです。
でも、フェイクニュースや陰謀論にだまされないためには、自分がもともと持っている意見や考え方を「ちょっと疑ってみる」ことが重要だと心理学では考えられています。
この研究で使われた「認知ワクチン」というのは、自分の意見や考え方をすぐに信じ込まないように促す短いメッセージのことです。
今回の実験では、この短いメッセージを読んだだけで、自分の意見を「絶対に正しい」と決めつける態度が減り、情報を冷静に判断できるようになることがわかりました。
この考え方の柔軟性を高める方法は、特定のニュースやデマに限定されるのではなく、色々な種類の誤った情報に対して幅広く役立つ「心のワクチン」になる可能性があります。
今までの研究や教育方法の多くは、特定のテーマ(例えばコロナのデマなど)についてのみ注意を呼びかけるものでしたが、今回は「考え方そのもの」を変えることで、新しく出てきた別の話題にも対応できる方法だと言えます。
また、この方法は難しいトレーニングや特別な道具を使わず、文章を読ませるというシンプルな方法なので、学校の授業やSNSなどで簡単に導入できる可能性もあります。
ただし、実際に多くの人が使うためには、より短くてわかりやすい表現にするなどの工夫や、導入するための費用や手間についても今後詳しく調べる必要があります。
一方で、このワクチンの効果には注意すべきポイントもあります。
今回の実験の結果、情報を慎重に疑う態度が強くなるあまり、study2では少しだけ「全体的な不信感」が高まるという副作用も見られました。
研究チームはこれを「だまされにくくなった」という良い面として捉えていますが、あまりにも疑いすぎると、社会全体で必要な信頼関係まで壊してしまう可能性もあります。
そのため、このワクチンを広く使うときには、副作用が起きないかどうかを慎重に見守りながら進める必要があるでしょう。
さらに、今回の研究チームは、一回だけの短いメッセージで終わりにするのではなく、時間をおいて定期的に「思い出すための短いメッセージ(リマインダー)」をくり返すことで、効果がもっと長持ちするかもしれないとも考えています。
これは「ブースター接種」と呼ばれる本物のワクチンの仕組みと似ていて、何度か同じ内容をくり返すことで免疫力を維持する考え方を利用したものです。
まとめると、この研究が示しているのは、フェイクニュースや陰謀論に負けないためには、「自分の考えをちょっと疑う」という小さな習慣が何よりも大切だということです。
一度に強力な効果を求めるのではなく、日常の中で筋トレのように少しずつ考える力を鍛えていくことが、最終的には大きな力となって私たちをフェイク情報から守ってくれるかもしれません。
元論文
Norm-enhanced prebunking for actively open-minded thinking indirectly improves misinformation discernment and reduces conspiracy beliefs
https://doi.org/10.1016/j.jesp.2025.104818
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部
