アメリカの南カリフォルニア大学(USC)などで行われた研究により、海底の微生物たちがまるで脳のような電気ネットワークを形成し電子をやりとりしている可能性が示されました。
研究者たちは、この不思議な電気ネットワークのお陰で微生物はメタンを効率よく分解する能力を獲得しており、海底から流出するメタンが大気に出る前に減らすことができていると考えています。
目に見えない「微生物ネットワーク」は、どんな理屈で地球の温暖化ガスを食い止めているのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年8月22日に『Science Advances』にて発表されました。
目次
- 海底から消えるメタンの謎を追って
- 電気を送り合う微生物たち
- 電子リレー発見の意義と今後の課題
海底から消えるメタンの謎を追って

メタンという気体は地球温暖化を進める原因の一つで、「温室効果ガス」と呼ばれています。
中でもメタンは、同じ温室効果ガスとしてよく知られる二酸化炭素に比べて、地球を温める力が非常に強いことが分かっています。
そのメタンは、実は海底の地下深くから絶えず湧き出しています。
こう聞くと「大量のメタンが大気に出ているのでは?」と思うかもしれませんが、実際には、そのうちの一部しか海面を通じて空気中に出てきません。
なぜなら、海底には「メタンを食べる微生物たち」がいるからです。
酸素のない海底の泥の中で、目に見えないほど小さな微生物たちが、湧き出してきたメタンを餌として消費しているのです。
まるで見えないフィルターのように働き、温暖化の原因になるメタンを途中で止めてくれているのです。
ただし、微生物ならどれでもメタンを分解できるというわけではありません。
実際にメタンを分解しているのは、海底に住む「メタン食い古細菌(メタン酸化古細菌、ANME)」と呼ばれる種類の微生物です。
しかし、この古細菌だけではメタンの分解を完全に行うことができません。
メタンを分解してエネルギーを取り出したとき、「電子」という小さなエネルギーの粒が細胞内に溜まってしまうのです。
電子が溜まりすぎると細胞にとって良くないため、安全に細胞の外に出す必要があります。
れは私たち人間の呼吸と非常によく似ています。
呼吸と言えば一般には「必要な酸素を吸って不要な二酸化炭素を排出すること」と思われがちですが、電子の動きを見ると別の解釈が可能です。
私たちが食べ物を食べるのは、生きるために必要なエネルギーを体内で取り出すためですが、そのエネルギーを取り出す過程で、小さな「電子」という粒子が発生します。
この電子はエネルギーを得るためには必要なものですが、体内にずっと溜まり続けると細胞にとって有害になってしまいます。
そこで人間の体は、酸素を利用して、このいらなくなった電子をうまく処理しています。
私たちは肺で酸素を取り入れますが、実はその酸素の役割は、この余った電子を受け取って安全な形で体の外に運び出すことなのです。
つまり呼吸を電子の視点から視ると『いらない電子を安全に外へ出す作業』でもあるわけです。
メタンを食べる古細菌にも、同じような電子の処理方法が必要になります。
しかし、この古細菌は人間のように酸素を使って電子を処理することができません。
海底の泥の中には酸素がないからです。
では、どうやって古細菌は電子を安全に細胞の外に出しているのでしょうか?
実はここで重要な役割を果たしているのが、もう一種類の微生物である「硫酸還元菌(SRB)」です。
硫酸還元菌は、隣にいる古細菌が処理しきれない電子を受け取り、その電子を海水中にある「硫酸」という物質に渡すことで自分のエネルギーを得ています。
こうして古細菌と硫酸還元菌の2種類の微生物がタッグを組むことで、メタンと硫酸が同時に消費され、お互いに協力しなければできない特別な化学反応が実現しているのです。
ただし、この「電子のやりとり」が具体的にどうやって行われているかは、長年の謎でした。
電子というのは、目に見えないほど小さく直接観察するのが難しいからです。
科学者たちは以前から、「この微生物ペアは電気的なつながりによって協力しているのでは?」と予想していました。
たとえば、細菌が細い電線(ナノワイヤー)を伸ばしてつながっているのではないか、あるいは特別な粒子やタンパク質が電子を運んでいるのではないか、と考えられていました。
しかし、実際にこの電子のやり取りを直接証明することはとても難しく、長い間確かな証拠は得られませんでした。
そこで今回の研究チームは、この微生物のペアが本当に電子をやり取りしているのか、またそれがどのように行われているのかを、科学的にしっかり解明しようと試みました。
電気を送り合う微生物たち

今回の研究チームは、海底でメタンを分解する2種類の微生物のペアに着目しました。
1つはメタンを食べる特殊な古細菌(嫌気性メタン酸化古細菌)で、もう1つはその相棒となる硫酸還元菌という細菌です。
これらの微生物は、普段は海底の泥の中で多くの他の生物や物質に囲まれて暮らしています。
しかし、このままの状態では、微生物自身の特徴や働きを正確に調べることが難しいため、
研究チームは「微生物だけを増やす培養」を行いました。
この培養では、海底の泥やその他の生き物などの余分なものを取り除いて、
目的とする微生物のペアを中心に増やしました。
電気を通すかどうかを調べるには、微生物の塊を小さな電極につなぎ、電気の流れを測定します。
ちょうど電気の通り道をテストするようなものです。
その結果、なんと微生物の塊は電気をよく通すことがわかりました。
細胞同士がつながって一つの電子回路になっているかのように、電子がスムーズに移動していたのです。
しかし、「なぜ微生物は電気を通せるのか?」という疑問が残りました。
そこで研究チームは、微生物が電気を通す仕組みを詳しく調べることにしました。
まず考えられたのは、微生物が金属のような単純な導線の仕組みで電子を運んでいる可能性でした。
もし金属のような単純な仕組みであれば、電気を流すとき電圧を高くすると、それに比例して電流も高くなるはずです。
しかし実際に微生物でテストしてみると、電流は単純に電圧に比例して増えるわけではありませんでした。
代わりに、特定の電圧のところで、はっきりとした「山」のようなピークが現れました。
この「ピーク」の意味は何でしょう?
これは微生物が、特定の電圧付近でしか電子を受け取ったり渡したりできないことを示しています。
例えるなら、電子を手渡しするリレーが微生物の中で行われているようなもので、自由に電子が通れる金属の導線とは違っていたのです。
さらに詳しく調べると、このピークの性質は「マルチヘムc型シトクロム」というタンパク質の特徴とよく似ていることがわかりました。
このタンパク質は、細胞内外で電子を受け取ったり渡したりする役割を持つことが知られています。
つまり微生物は、細胞の中にタンパク質でできた電子リレー(バケツリレーのような仕組み)を持っている可能性が示唆されたのです。
ですが決定的となったのは、電子が実際に微生物から微生物へ移動していることを直接確かめる実験でした。
実験では、微生物の塊の片側の端から電子を送り込み、反対側の端でその電子が出てくるかを調べました。
すると、片方の端で送り込んだ電子信号が、微生物の細胞間を通ってもう片方の端まで届いていることが確認されました。
その距離は数マイクロメートルで、これは古細菌と硫酸還元菌が細胞間で電子をやり取りするのに十分な距離です。
この結果は非常に重要です。
研究チームは、これがメタン分解を担う微生物たちの共生を支える重要な手がかりとなり、これまで仮説にとどまっていた『細胞間の電子輸送(レドックス伝導)』を実際の測定で示した成果だと考えています。
電子リレー発見の意義と今後の課題
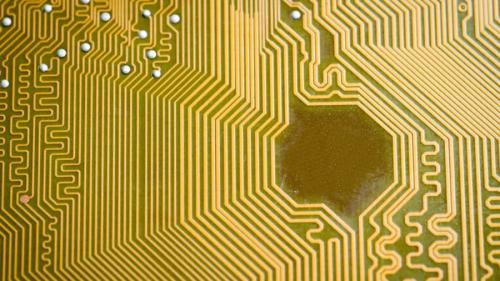
今回の研究は、海底の微生物たちが実際に電気を介して助け合っていることを、初めて電気的な測定によって直接的な証拠を示しました。
長年仮説に過ぎなかった「電気共生」が事実であり、その仕組みはタンパク質による電子リレー(レドックス伝達)である可能性が高いと示したのです。
少なくともこのメタン分解コンビにおいて、以前に議論されていたナノワイヤーのような金属配線よりも、タンパク質が主役のネットワークだと言えます。
これは、生態学的にも地球環境的にも重要な意味を持ちます。
微生物同士が電気回路を形成する共生という、一見SFのような現象は実際に存在し、地球上のメタン循環に深く関わっているのです。
見方を変えれば、この微生物コンビは小さな「脳」のようだとも言えるでしょう。
異なる細胞同士が電気信号(電子)のやり取りで緊密に連絡を取り合い、一つの目的(メタンの分解)のために協調しているからです。
もちろん実際の脳とは仕組みが違いますが、遠く離れた深海底にもこれほど精巧なコミュニケーションが存在することには驚かされます。
カリフォルニア工科大学の環境科学・地球生物学教授であるヴィクトリア・オーファン氏は、「微生物が人里離れた場所でもお互いに高度に協力しており、その活動が地球規模のプロセスに影響していることに驚く人もいるでしょう。今回の発見は10年近い多くの分野が協力した研究の成果であり、科学における忍耐と協力の大切さを示しています。私たちが頼っている微生物の生態系には、まだ解明されていないことがたくさん残っています」と述べています。
誰も目にすることのない海底で、小さな微生物がせっせとメタンを食べて地球を冷やしてくれていると考えると、私たちが普段何気なく吸っている澄んだ空気も、彼らがいるからこそ保たれているのかもしれません。
さらに、この発見は地球環境の保全にも新たなヒントを与えてくれます。
メタンは二酸化炭素より温室効果が強いため、削減が重要視される気体です。自然界では海底の微生物たちが毎年大量のメタンを生きたフィルターのように捕まえて消費し、大気への放出を防いでいます。
研究によれば、海底由来のメタンの多くがこうした微生物によって酸化されていると考えられます。
研究チームは、この仕組みを理解することで「温室効果ガスであるメタンの排出を抑制する新たな手段につながる可能性がある」と期待しています。
地球温暖化対策というと先端技術に目が向きがちですが、実は私たちの知らないところで小さな微生物たちが重要な役割を果たしているのです。
さらに学術的な観点では、同様の電気的共生関係が他の環境中にも存在するのか、新種の「電気を通す微生物」が他にもいるのかといった新たな疑問も生まれます。
実際、過去には淡水環境に棲む別種の古細菌(ANME-2d)が似たような多ヘムシトクロムを使って金属に電子を渡す仕組みを持つことが報告されており、今後さらに未知の電気的な微生物同盟が見つかるかもしれません。
参考文献
Scientists reveal how microbes collaborate to consume potent greenhouse gas
https://dornsife.usc.edu/news/stories/microbes-collaborate-to-consume-ocean-methane/?utm_source=chatgpt.com
元論文
Redox conduction facilitates direct interspecies electron transport in anaerobic methanotrophic consortia
https://doi.org/10.1126/sciadv.adw4289
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部
