皆さんは好きな曲を聴いた瞬間、その時の気持ちや風景まで一緒に蘇ってきた経験はないでしょうか。
近年になって音楽と記憶の関係がかなり深いことがわかってきています。
ですが今回、アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で行われた新しい研究によって、物事を覚えた直後に音楽を聴くと、その音楽によって引き起こされた感情の高まり方によって記憶力が変化することが明らかになりました。
興味深いことに、この研究では、感情がほどよく高まったときには細かな情報の記憶力が向上した一方、感情が強すぎたり、逆に低すぎたりすると、細部の記憶がむしろ弱まってしまうという「感情の最適レベル」が存在することが示されたのです。
音楽が記憶力を改善するということは、以前からよく知られていますが、なぜ「ちょうどいい感情の盛り上がり」がこれほど重要なのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年7月30日に『The Journal of Neuroscience』にて発表されました。
目次
- 記憶を揺さぶる音楽と感情の関係
- ほどよい音楽の興奮が細部記憶を強化する
- 感情のスイッチで記憶を使い分ける未来
記憶を揺さぶる音楽と感情の関係

私たちの身の回りには、いつも音楽が流れています。
映画の主題歌を聴けば、その映画の感動的なシーンが浮かんできますし、懐かしい曲を聴くと、まるでタイムマシンに乗ったように、昔の出来事や気持ちがよみがえることもあります。
このように、音楽と記憶はとても密接に結びついています。
でも、どうして音楽を聴くだけで昔のことが鮮明に思い出せるのでしょうか?
実はその秘密は、音楽が私たちの感情を強く揺さぶるからです。
例えば、好きな曲を聴いているとワクワクしたり、悲しい曲を聴いていると切なくなったりしますよね。
音楽がこうした感情を呼び起こすとき、脳の中では特別なホルモンが出ています。
これらのホルモンは、記憶の司令塔である「海馬(かいば)」や、感情の中枢である「扁桃体(へんとうたい)」といった脳の場所に作用して、「この出来事は大事だから、しっかり覚えておこう!」と脳に命令を出すのです。
嬉しかった日や悲しかった日のことがよく記憶に残っているのは、このように感情が動いたときに、ホルモンが脳に働きかけているためです。
これを利用して、「音楽を聴いて気持ちを盛り上げれば、記憶がより強く残るのでは?」と考える科学者もいます。
実際、アルツハイマー病のように記憶力が落ちてしまう病気や、不安症やPTSD(心的外傷後ストレス障害)のような、辛い記憶に苦しむ人たちに対して、音楽を用いた新しい治療法が提案されてきました。
ただし、現時点ではまだ病院などでの効果ははっきりとは証明されていません。
あくまでも、「音楽で記憶を良くできるかもしれない」という段階なのです。
一方で、感情による記憶の強化は、いつでも必ず起こるとは限りません。
例えば、スポーツやテストの前に緊張や興奮しすぎると、頭が真っ白になってうまくいかないことがありますよね。
これは、興奮や緊張が強すぎたり、逆に気が抜けすぎたりすると、脳の力が発揮できなくなるという現象です。
心理学の世界では、このような現象を「ヤーキーズ・ドッドソンの法則」と呼んでいます。
この法則によると、人がもっとも高い力を出せるのは、「適度に緊張したり興奮したりしている時」であり、緊張や興奮が強すぎたり弱すぎたりすると、むしろ力が出なくなることが知られています。
また、感情が非常に強く動くような体験では、記憶にも面白い変化が起きます。
例えば、大勢の前で発表をしたときを想像してみましょう。
緊張して胸がドキドキしていたら、その時の出来事は強く覚えていますよね。
でも後で「あのとき何て質問されたかな?」などの細かな部分は思い出せなかったりします。
つまり、強い感情が動くときは、大まかな全体像(全体記憶)はしっかりと記憶に残る一方で、細かな部分(細部記憶)は忘れやすくなってしまうという特徴があります。
言い換えると、「細かなことよりも、ざっくりと覚える」ように脳が働くのです。
では、音楽の場合はどうでしょうか?
音楽には感情を動かす力がありますが、その感じ方は人それぞれです。
同じ音楽を聴いても、「とてもワクワクする」という人もいれば、「落ち着いた気持ちになる」という人もいるでしょう。
そこで今回の研究チームは、「記憶を覚えた直後に音楽を流したら、どんな影響があるのか?」という疑問を、詳しく調べることにしました。
特に重要なのが「記憶した直後」のタイミングです。
私たちの脳は、何か新しい情報を覚えた後、その記憶を整理してしっかりと定着させようとします。
そこでこのタイミングで音楽という刺激を与えれば、記憶の固定のされ方を変えられるかもしれない──これが研究の狙いでした。
ほどよい音楽の興奮が細部記憶を強化する
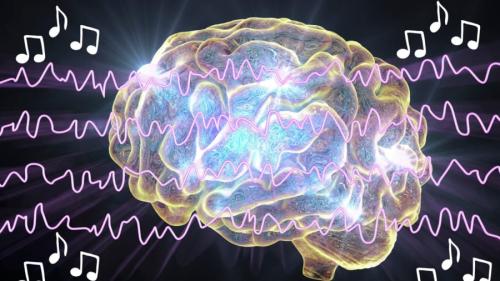
今回の研究チームが明らかにしようとしたのは、音楽が「実際にどのように記憶に影響を与えるか」ということです。
しかし、記憶といっても、実はいろんな種類があります。
たとえば、「昨日の晩ごはんは何を食べたか?」を思い出すとき、細かな食材まで鮮明に覚えていることもあれば、ざっくりと「お肉料理だったかな?」というふうに、大まかにしか覚えていないこともありますよね。
心理学の研究では、このような違いを区別して考えます。
つまり、記憶には「細かな違いや細部まできっちり覚えるタイプの記憶(細部記憶)」と、「大体の内容やざっくりとした印象だけ覚えているタイプの記憶(全体記憶)」という2種類があるとされています。
研究チームが注目したのは、「音楽を聴いて気分が高まったり落ち着いたりすることで、この2種類の記憶にそれぞれ異なった影響が出るのでは?」という点です。
そのために今回の実験では、まず参加者に「日常的によく見かけるもの」の写真をいくつも見てもらいました。
電話やノートパソコン、オレンジといった、誰もが見たことのある身近なものです。
ひと通り見終わった後、被験者たちは6つの条件のうちのどれかに分けられました。
4つの条件はクラシック音楽で、「明るい曲か暗い曲か」「なじみがあるかないか」の組み合わせによるものでした。
残りの2つの条件は、「流れる水の音や飛行機の中の環境音、暖炉の火がパチパチとはぜる音などの中立的な音」と「無音(音なし)」です。
また、比較のために「流れる水の音」「飛行機内の環境音」「暖炉の火がパチパチとはぜる音」といった感情をそれほど動かさない中立的な音や、「まったく音がない(無音)」という条件も用意しました。
これらいろいろな条件を用意した理由は、「音楽の種類そのものよりも、音楽を聴いて人が感じる気持ちの変化(どのくらいドキドキするか)が、記憶に影響を与えるかもしれない」と考えたからです。
実験のあと、参加者には「写真の記憶をチェックするテスト」を受けてもらいました。
参加者は、前に見た写真と全く同じ写真や、似ているけれど少しだけ違う写真、そして全く見たことのない新しい写真などを見せられました。
ここで参加者に聞いた質問はシンプルです。
「この写真はさっき見ましたか?」について「見た/見ていない」の二択で答えてもらいます。
「似ている写真」を見ているときに、「あれ、さっき見た写真と似ているけど、ちょっと違うぞ!」と細かい違いに気づければ、「細部まで詳しく覚えている」証拠です。
逆に、細かい違いに気づけず「これはさっき見たのと同じ!」と答える人は、「ざっくりとした全体だけを覚えている」ということになります。
研究の結果、この記憶テストで非常に興味深いことがわかりました。
それは、音楽を聴いたあとに感じた「ドキドキの度合い」が、「細かく覚える記憶」と「ざっくり覚える記憶」に大きく関係しているということです。
特に重要なのが、「音楽で気持ちがほどよく高まった(ドキドキがちょうど良い)人」です。
そういった人は、「細かな違いを見分ける力(細部記憶)」が高まりました。
ところが、その反面、「ざっくりとした全体を覚える力(全体記憶)」は少し下がってしまったのです。
つまり、気持ちがちょうどよく高まったときには、記憶が「細部を覚えるモード」になりやすかったわけです。
一方で、音楽を聴いて「すごく興奮した人」や、逆に「ほとんど何も感じなかった人」もいました。
このようにドキドキの度合いが極端(高すぎる/低すぎる)な人は、逆に細かな違いを見分ける力が低下し、写真の全体像やざっくりとした印象だけを覚える傾向が強まりました。
つまり、極端な気持ちの状態では、記憶は「ざっくりとした全体を覚えるモード」に切り替わったのです。
また、「音楽を聴いたら全員の記憶力が一律にアップするわけではない」ということもわかりました。
それぞれの人が「どれだけドキドキしたか」という感じ方が、記憶の変化に決定的な影響を与えていました。
音楽が明るいか暗いか、知っている曲か知らない曲かということ自体は、それほど重要ではなかったのです。
この結果は、心理学で有名な「ヤーキーズ・ドッドソンの法則」(人の能力は中くらいの興奮度のとき最も高くなり、興奮しすぎたり緊張しすぎたりすると下がる)を裏付けるものでした。
ただし、この研究が新しく示した重要なポイントがあります。
それは、「記憶の種類によって、ベストな興奮度が違う可能性がある」ということです。
つまり、「細かな違いをしっかり覚える」ためにはちょうどよいドキドキが必要ですが、「ざっくりと大まかに覚える」ためには、むしろ極端に気持ちが高まったり低くなったりする方が効果的かもしれないということなのです。
この発見は、音楽を使って記憶のタイプを調整できる可能性を示すもので、これまでの研究よりも一歩進んだ内容となっています。
感情のスイッチで記憶を使い分ける未来
今回の研究によって「音楽と記憶力」の関係は、音楽がアリなら記憶力が上がり、ナシなら下がるという単純なものではなく、記憶の中身によって効果が異なることが示されました。
どういうことかというと、音楽が記憶に与える影響は、「どんな記憶を残したいか?」という目的によって違ってくるということなのです。
たとえば、あなたがテストのために勉強をした後を想像してみてください。
その直後に「ちょうど良いテンション」を感じられるような曲を聴くと、勉強した内容の細かい部分がしっかり記憶に残りやすくなります。
でも、もし「すごく興奮してしまう」曲を聴いたらどうなるでしょうか。
実は、細かな内容よりも「ざっくりとした大筋の内容」だけが記憶に残って、細かな部分は忘れやすくなってしまうのです。
ある意味で、音楽は単純に記憶力を上げる道具というよりは、「記憶をどのくらい細かく残すかを調整するツマミ」のような役割を持っていると言えるでしょう。
これは音楽を聴けば何でも覚えられるという魔法のような話ではありませんが、うまく使えば、自分が必要とするタイプの記憶を強化することができる可能性があるということを示しています。
実際に研究者たちは、記憶には「細かい記憶(細部記憶)」と「大まかな記憶(全体記憶)」の二つの種類があり、音楽を聴いて感じる「ドキドキの度合い」によって、この二つが逆方向に影響されることを見つけました。
つまり、「ほどほどにドキドキした人」は細かな記憶が良くなり、「ドキドキが強すぎたり弱すぎたりした人」は大まかな記憶の方が良くなったのです。
これは今まであまり知られていなかった重要な発見です。
さらに、この新たな知見は、将来的に医療や心理療法にも役立つ可能性があります。
例えば、不安症やPTSD(心的外傷後ストレス障害)などにつながる辛い出来事を経験した直後に「あえて感情を強く揺さぶるような曲」を聴いてもらうことで、辛い出来事の細かい部分をぼかし、大まかな記憶だけを残して、ショックや辛さを和らげることができるかもしれません。
ただし、音楽によって感じる「ちょうど良いドキドキ感」は、人それぞれ全く違います。
同じ曲を聴いても、ある人はリラックスし、ある人は興奮しすぎてしまうように、曲の感じ方は人それぞれなのです。
実際、今回の研究でも、参加者たちはみんな違う反応をしました。
ある人にとってちょうど良い曲が、別の人には強すぎたり、逆に物足りなかったりすることがありました。
つまり、この方法を実際に記憶力の向上に使おうとするときには、「その人にとってちょうど良い曲と興奮の度合い」を見つけることが重要なのです。
研究者たちも今後この技術を普及させるには、さらに詳しい調査が必要だと考えています。
例えば、今回の研究は大学生だけを対象にしましたが、他の年齢層でも同じような効果があるかはまだわかっていません。
また、心拍数や瞳孔の開き具合など、「身体の反応」を測ることで、その人がどれだけ興奮しているかをより客観的に測定することも検討されています。
さらに、記憶が音楽によってどのくらい長期間保持されるのかや、クラシック以外のさまざまなジャンルの音楽でも同じ効果があるのかを調べる必要もあるでしょう。
このようにデータをたくさん集めることで、将来的には「あなたにはこの曲がベスト!」という、一人ひとりにぴったりの「音楽処方箋」のようなものを作れるかもしれません。
実際、今回の研究を率いたリール教授は「音楽には、治療の目的に応じて記憶を強めたり弱めたりすることが可能かもしれません」と述べています。
音楽は身近で気軽に楽しめるものでありながら、記憶という私たちの大切な機能をコントロールするツールとして、大きな可能性を秘めていることがわかります。
今回の研究は、音楽の持つこの新しい可能性を示した重要な一歩となっています。
元論文
Fine-Tuning the Details: Post-encoding Music Differentially Impacts General and Detailed Memory
https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0158-25.2025
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部
