アメリカのネバダ大学などで行われた研究により、金の通常の融点(約1337ケルビン、摂氏約1064℃)の14倍にも相当する約1万9000ケルビン(摂氏約1万8700℃)の超高温状態でも、金が固体のまま結晶構造を維持できたことが明らかになりました。
この状態になると、固体のほうが液体の状態よりも乱雑さ(エントロピー)が高いという逆転が起きてしまいます。
研究者の1人であるホワイト氏は「本当にこんな高温でも溶けないのか」と驚きを隠せなかったと述べています。
なぜ融点の14倍に達しても金は融けなかったのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年7月23日に『Nature』にて発表されました。
目次
- 電子レンジの「突沸」と金属の「過加熱」の意外な共通点
- 金はなぜ融点の14倍でも「固体」を保てたのか?
- 【まとめ】常識を超えた金の超加熱が世界をどう変えるか
電子レンジの「突沸」と金属の「過加熱」の意外な共通点

例えば電子レンジで水を温めるとき、設定時間を間違えて少し加熱しすぎてしまったことはありませんか?
水は本来100℃で沸騰しますが、表面がとても滑らかな容器で慎重に加熱すると、実は100℃を超えても沸騰しないことがあります。
しかし、いざ容器を取り出そうとすると、わずかな振動や刺激によって一気に激しく沸騰してしまうことがあるのです。
これは「突沸(とっぷつ)」と呼ばれる現象で、実際に経験すると大変驚きますし、ときには火傷をすることもあります。
(※筆者が小中学校のときの理科の実験では、このような突沸を防ぐため「沸騰石」を使用した記憶があります。沸騰石は凹凸が多く過加熱を防ぎ適度な温度での沸騰を促します)
こうした現象は「過加熱(かかねつ)」と呼ばれていて、水のような液体が気体になるときだけではなく、固体から液体に溶けるときにも起こることが知られています。
一方で私たちは、小学校の理科の授業以来、物質には決まった融点(固体が液体に変わる温度)や沸点(液体が気体に変わる温度)があると教えられてきました。
例えば氷は0℃で水になり、水は100℃で蒸発して気体になる、という具合です。
このような変化を「相転移(そうてんい)」と呼び、温度や圧力などの条件が整えば物質は必ず状態を変えるとされています。
しかし、実際には条件次第で融点や沸点を超えてもなかなか相転移を起こさないことがあり、これが前述した「過加熱」や「過冷却(かれいきゃく)」のような不思議な現象を引き起こします。
ではなぜこのような現象が起きるのでしょうか。
それは、物質が状態を変えるときには必ず何らかの「きっかけ」が必要だからです。
通常、液体が沸騰する場合ならば、小さな泡が容器の表面や不純物などを起点にして生じます。
しかし、滑らかな容器でゆっくり加熱した場合、泡が生じるきっかけがなかなか起きず、100℃を超えても液体の状態が保たれてしまうのです。
そして、ほんの少しの衝撃がきっかけとなり、一気に沸騰する現象が起きるわけです。
固体の場合もこれと似ています。
純度が高い金属や結晶をきっかけが起こらないように丁寧に加熱すると、一時的に融点を超えても固体の状態を維持できると理論的には考えられてきました。
しかし、こうした「固体の過加熱」は極めて不安定で、ほんのわずかな刺激で急激に融解し、液体へと変化してしまいます。
この突然の崩壊は「カタストロフィー(破局)」と呼ばれ、固体内部に蓄えられた熱エネルギーが一気に放出されることで生じます。
また、温度が上がれば上がるほど、崩壊のきっかけとなる小さな乱れが起きやすくなるため、実際にはある温度以上の「超高温の領域」では固体を安定させることは難しいと考えられてきました。
そこで物理学者たちは、「固体が存在できる究極の温度限界」を理論的に探求し始めました。
この研究が本格的に始まったのは約40年前のことで、その核心となったのが「エントロピー破局(Entropy Catastrophe)」という概念です。
「エントロピー」とは聞き慣れない言葉ですが、これは物質の中の「乱雑さ」や「無秩序さ」を表す熱力学の用語です。
例えば、氷は原子が規則正しく並んでいるためエントロピーが低く、一方で水は自由に動き回るためエントロピーが高い状態になります。
しかし物理学者たちが理論的に計算を進めると、不思議な予測が現れました。
固体をさらに高温にしながら、それでもあえて「液体にさせない」条件を考えたとき、固体のエントロピーがどんどん増加していくことが示されたのです。
これは、原子がまだ整然と並んでいるにもかかわらず、その並び方を保ったまま激しく動き、結果として固体内部に非常に多くのエネルギーが溜まり、乱雑さ(エントロピー)が大きくなってしまうからです。
そうなると、ある極めて高い温度で、とうとう固体のエントロピーが液体のエントロピーに追いつき、それを超えてしまう状況が理論上想定されます。
もしも固体の方が液体よりもエントロピーが高くなるとしたら、どうなるでしょうか?
固体が液体よりも「乱雑」だということになり、熱力学の基本原則である「エントロピーは常に増える方向に進む」という第二法則に矛盾してしまいます。
なぜなら、もしそんな状態が可能だとすると、エネルギー的に安定な液体に向かって状態が移ることなく、不安定で乱雑な状態のまま固体で存在し続けてしまうことになるからです。
これは熱力学では許されない、ありえない状況なのです。
こうした熱力学の矛盾が生じる理論的な限界点こそが、物理学者たちが「エントロピー破局」と呼んでいるものです。
計算によれば、多くの物質の場合、この限界となる温度はおよそ「融点の3倍程度」だと予想されてきました。
しかし、この理論的な限界を実験で証明するのは非常に難しく、40年間にわたり科学者たちはさまざまな実験を行いましたが、誰一人として成功していませんでした。
なぜなら、実際に固体を極端に高温へ加熱すると、エントロピー破局に到達する前に、必ず別の要因(小さな欠陥や表面の融解など)によって固体が崩壊し、液体になってしまったからです。
ある意味で理論的な限界は存在するけれども、誰もその「究極の限界」を目にしたことがなく、それはまるで「蜃気楼のような幻の限界」だったと言えるでしょう。
こうした長年の疑問に、今回の研究チームが新たな視点で挑みました。
これまでの研究とは全く異なる特殊な条件を作り出すことで、エントロピー破局を回避し、「固体の限界」を突破しようと試みたのです。
研究者たちは本当に「固体の限界」を超えることができたのでしょうか?
金はなぜ融点の14倍でも「固体」を保てたのか?
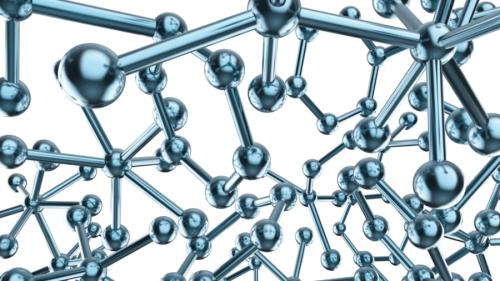
固体の温度限界を超えることなど、本当に可能なのか?
この謎を解明するため研究者たちはまず、非常に純粋で、厚さがわずか50ナノメートル(ナノメートルは1メートルの10億分の1)という、極薄の金の薄膜を準備しました。
なぜここまで薄くする必要があるのかというと、金属が厚いと熱が内部まで伝わるのに時間がかかってしまい、瞬間的な高温加熱の条件を作り出せないからです。
極薄の薄膜であれば、一瞬で熱が金属全体に伝わり、均一で安定した実験条件を作ることができます。
次に、この極薄の金の薄膜に対して、「超高速レーザー」という非常に短い時間で強力なエネルギーを与えられる特殊な装置を使って熱を加えました。
このレーザーが薄膜を加熱する時間はわずか45フェムト秒です。
フェムト秒とは、1秒を1000兆分の1にした極めて短い時間で、これは光が人間の髪の毛1本の幅を横切るのにかかる時間よりもさらに短いほどの一瞬です。
想像を絶する短さですが、この一瞬の間に金の薄膜に非常に大きなエネルギーが集中して与えられ、温度が急激に跳ね上がるのです。
しかしここで一つの疑問が生じます。
これほどまでに一瞬で温度が上がったかどうかを、どのようにして測定するのでしょうか?
実際の温度計ではとうてい測ることができない短時間での超高温を、研究者たちはどうやって正確に把握したのでしょうか?
この答えとして研究チームが考え出したのは、物質の原子の動きを直接測定するという非常に画期的な方法でした。
原子は熱が高くなればなるほど激しく振動する性質があり、その振動の大きさやスピードを測定できれば、そのまま物質の温度を知ることができるというわけです。
具体的には、超高輝度のX線レーザー(SLACのLCLS:リーナック・コヒーレント・ライト・ソース)を金の薄膜に照射し、金の原子にぶつかって散乱したX線を詳細に解析しました。
この散乱したX線は、原子が激しく動いているほど微妙にエネルギーが変化します。
その変化の度合いを精密に計測することで、研究者たちは、超高温状態にある金原子の正確な振動速度を知ることができたのです。
言い換えれば、原子の振動を直接「見る」ことで、物質の温度を測る「究極の温度計」を手にしたことになります。
こうした工夫により、研究者たちは、これまで誰も測ることができなかった領域の温度を初めて正確に測定することに成功しました。
その結果、驚くべきことが判明しました。
金の薄膜の温度は、なんと約1万9000ケルビン(摂氏約1万8700℃)にまで達していたのです。
これは金が通常溶ける温度(融点)である約1337ケルビン(摂氏1064℃)の14倍という途方もない高温で、従来の理論が予想していた「エントロピー破局の限界」(融点の約3倍)をはるかに超えていました。
さらに驚いたことに、このような極端な高温状態であるにもかかわらず、金はすぐには融解せず、短時間ではありますが固体のままの構造を維持したのです。
実験を行った研究者自身も、この結果には強い疑いを持ったといいます。
データに何らかの間違いがないかと繰り返し確認したほどでしたが、どれだけ調べても測定結果は変わりませんでした。
では、なぜ金はこのような高温でも溶けることなく、固体の構造を保つことができたのでしょうか?
この謎を解く鍵は、研究チームが用いた「超高速加熱」という特殊な方法にありました。
通常、固体が液体になる「融解」という現象は、原子が熱エネルギーを得て動き回り、互いの距離が広がっていくことで起こります。
これは原子が規則的に並んだ「結晶構造」が崩れることを意味しますが、その変化が起きるためには、ある程度の時間的余裕が必要です。
しかし今回は、あまりにも短時間で急激に熱エネルギーが加えられたため、原子が結晶構造を崩したり、互いの距離を広げる暇が全くありませんでした。
言い換えると、原子たちは非常に激しく振動したものの、結晶構造そのものはまるで時間が止まったかのように崩れず、そのため一時的に超高温のまま固体でいることが可能になったのです。
この結果は、一見すると物理の基本的な法則(特に熱力学の第二法則)に反しているように見えますが、実はそうではありません。
熱力学の第二法則とは、エントロピー(物質の乱雑さ)は常に増える方向に進むというものです。
今回の実験条件は、あくまで非常に短時間の特殊な状況であり、平衡状態(物質が安定した状態)とは大きく異なります。
したがって、ホワイト氏も明確に「熱力学第二法則に反したわけではありません」と述べています。
つまり、極めて短時間(今回の場合は約45フェムト秒)に限って言えば、「エントロピー破局」と呼ばれる崩壊現象を回避し、理論的な限界を超えることが可能であることを実証したというわけです。
では、この驚くべき発見はどのような意味を持つのでしょうか?
固体の「限界」を突破することに成功したこの実験は、物理学の常識をどのように変えることになるのでしょうか?
【まとめ】常識を超えた金の超加熱が世界をどう変えるか
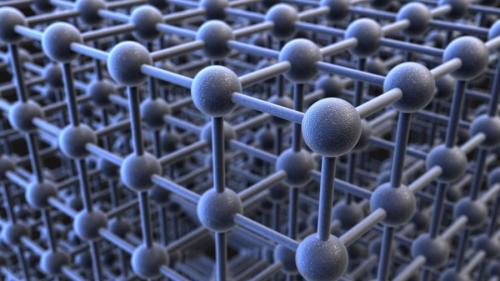
今回の研究によって、「固体の温度には限界がある」というこれまでの物理学の常識が、条件次第で簡単に超えられてしまう可能性が示されました。
この結果は、これまで40年以上にわたり物理学者たちが受け入れてきた考え方を大きく覆すもので、科学の世界に大きな衝撃を与えています。
「固体の限界」は本当に存在するのか、あるいは極めて短い時間だけであれば実質的に「無限」に近い温度まで固体が存在できるのかもしれない──今回の実験はそんな不思議な可能性を示唆しているのです。
まず、この研究が科学的に重要である一つ目の理由は、「エントロピー破局」という理論を実験的に超えたことです。
「エントロピー破局」とは、固体が極めて高い温度に達するとエントロピー(物質の乱雑さ)が液体より高くなり、理論上は固体が安定できなくなってしまう限界のことです。
しかし、今回の研究では超高速レーザーという特殊な方法を使うことで、この理論的な上限をあっさりと超えることができました。
つまり、「物質のエントロピーは常に増加する」という熱力学の基本的なルールに反しているように見えながらも、実際には非常に短い時間(約45フェムト秒)であれば、そのルールに抵触せず限界を超えられることを実証したのです。
もう一つ、この研究が持つ科学的な価値は、「新しい温度測定法を開発した」点にあります。
極端な高温や高圧といった「極限環境」での物質のふるまいを正確に理解するには、まずその環境下での温度を正しく測る必要があります。
しかしこれまでは、このような極限状態では温度を直接的に測ることは難しく、研究者は理論モデルや推測に頼るしかありませんでした。
今回の研究チームが採用したのは、X線レーザーを使って原子の振動を直接測ることで温度を導き出すという方法です。
これは言わば、極限状態での物質に直接触れることなく、その温度を正確に「のぞき見る」ことができる画期的な手法です。
研究者のボブ・ナグラー氏は、この手法により「これまで不確かだった高エネルギー密度物質の温度測定を飛躍的に改善できる」と指摘しています。
実際、この新しい手法によって、これまで見逃されてきた現象や、理論モデルでは予測できなかった未知の現象が今後明らかになる可能性もあります。
では、なぜこうした極限状態での研究がそれほど重要なのでしょうか?
一つには、このような研究が惑星の内部構造を理解する手がかりになるということがあります。
私たちが住む地球や、木星や土星といった巨大な惑星の中心部は、極めて高温で高圧な状態にあると考えられていますが、直接観測することは不可能です。
しかし、この実験で用いられた方法を利用すれば、実験室内で惑星内部の極限環境を再現し、その中で物質がどのようにふるまうかを正確に知ることができます。
実際に研究チームは、今年の夏にこの新たな手法を用いて惑星の内部を再現する実験にも着手しています。
さらにもう一つ、この研究が社会的に重要な理由は、核融合エネルギーの研究への貢献が期待される点にあります。
核融合とは、太陽がエネルギーを生み出す仕組みと同じように、非常に高温かつ高密度の環境で原子核が融合し、莫大なエネルギーを生み出す現象です。
核融合エネルギーは、将来的に人類にとって安全で持続可能なエネルギー源となることが期待されています。
核融合を実用化するためには、小さな燃料ターゲットをレーザーで一瞬で圧縮して高温高密度にする必要がありますが、その過程でターゲットがいつ融解し、どの程度の温度に達するかを正確に知ることが重要です。
今回の研究で確立された新しい温度測定法を使えば、このような核融合ターゲットの温度や状態の変化を非常に精密に測定できる可能性があります。
こうして見ていくと、この研究は単に物理学の基本的な理論を覆しただけでなく、私たちの宇宙やエネルギー問題に対する理解を深めるための重要な突破口を開いたことが分かります。
今回の実験結果を受けて、「では、他の物質でも同じ現象が起こるのだろうか?」「どこまで物質を加熱しても、本当に固体は崩れないのだろうか?」という新たな疑問が次々と生まれてきています。
物理学者たちがこれから取り組むべき課題は、まさにここにあると言えるでしょう。
元論文
Superheating gold beyond the predicted entropy catastrophe threshold
https://doi.org/10.1038/s41586-025-09253-y
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部
