インドのハリッシュチャンドラ研究所(HRI)とベルギーのブリュッセル自由大学(ULB)で行われた研究によって、「量子もつれ」という量子の世界特有の現象を、バケツリレーのように複数の粒子ペアへ次々と分け与えられる可能性が示されました。
これまで、量子もつれは「一度作ると一組の粒子間でしか利用できない」と考えられてきましたが、今回の研究では最初に作られた量子もつれを少しずつ切り分けていけば、理論的には無限のペアにもつれを分配できることが明らかになりました。
ただし、分配するペアが増えるほど各ペアが受け取れるもつれは微量になってしまうため、実用面での限界も存在するとのことです。
この「量子もつれのリレー」とも呼べる新たな発見は、私たちの未来にどのようなインパクトをもたらすのでしょうか?
研究内容の詳細は2023年7月7日に『Physical Review A』にて発表されました。
目次
- なぜ今、「量子もつれ」の再利用が求められるのか?
- 「量子もつれ」を複数ペアに渡す新技術――理論モデルで検証
- 【まとめ】「もつれ分配」の登場で量子通信はどう変わる?
なぜ今、「量子もつれ」の再利用が求められるのか?
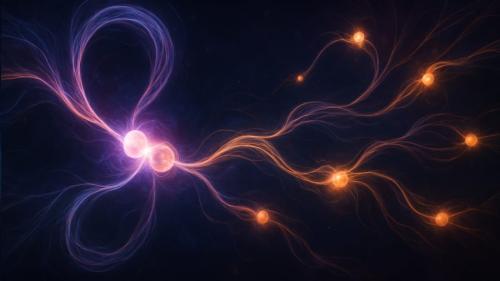
離れていても相手のことを感じられるような不思議なつながりを、誰もが一度くらいは想像したことがあるのではないでしょうか。
実は量子の世界では、粒子同士がまさにそんな見えない絆で結ばれることがあります。
この不思議な現象は「量子もつれ」と呼ばれ、ある粒子に変化を加えると、どんなに離れていてもペアになったもう一方の粒子が瞬時に影響を受ける、という奇妙な性質を持っています。
量子もつれの存在が初めて知られるようになったのは、今からおよそ90年も前、物理学者のアインシュタインたちが量子力学の理論に疑問を呈したときのことでした。
しかし、当初の疑念にもかかわらず、量子もつれはその後の実験で実在が証明され、現在では量子通信や量子暗号、量子テレポーテーションなど最先端技術の基盤となっています。
つまり、量子もつれは量子情報技術においてなくてはならない「資源」なのです。
しかし、この量子もつれという資源は生成するのが簡単ではありません。
一般的には、まず一つの場所で粒子同士を絡ませる特殊な操作を行ってもつれを作り出し、その後、その粒子を離れた二地点に届ける必要があります。
いわば一回の作業で使えるのは一組の利用者だけ、という不便さがありました。
これはちょうど、一度組んだ「糸」はその二人以外の誰とも再び結び直せない、というイメージに近いものです。
こうした現実の難しさがある中で、量子技術の利用が拡大するにつれて、貴重な量子もつれの資源をもっと効率よく、多くの利用者で共有できないかという問題が浮上してきました。
そこで研究者たちは次のような疑問を抱きました。
「すでに作られた一組のもつれを使って、複数のペアに順番にもつれを『分けて』いくことはできないだろうか?」
例えば、量子通信をしたいCさんとDさんがいて、彼らは今すぐにもつれを共有したいけれど自分たちだけではもつれを作り出せない状況を考えてみましょう。
ところが、少し離れた場所にいる別のペア(AさんとBさん)は既にもつれた状態を持っていて、これをうまく利用できるなら、わざわざ新しくもつれを作り直さなくても済むかもしれません。
もしCさんがAさんの粒子に接触し、DさんがBさんの粒子に接触することで、A–B間のもつれを活用しながら間接的にC–D間にもつれを作り出すことができたら、効率的だとは思いませんか?
実はこうしたアイデアは一見簡単そうですが、量子力学の理論的には意外と複雑な問題です。
なぜなら、一度あるペア(ここではC–Dペア)がもつれを受け取ってしまうと、元のA–Bペアが持つもつれは必ず一部失われてしまうからです。
また、もつれを渡す操作の過程では、AさんとCさんの粒子間や、BさんとDさんの粒子間にも新しいもつれ関係ができてしまうことがあります。
ところが、こうして生じた新しいもつれは、別のペアには利用できない性質を持っています。
言い換えると、こうした余計なもつれは「無駄」として蓄積され、貴重な資源が減ってしまうことにつながります。
これが繰り返されると、いつか必ずもつれが底をついてしまい、リレーが続けられなくなってしまう可能性があるのです。
果たして、もつれを渡し続けることには限界があるのでしょうか?
それとも、渡す量を小さくすればどこまでも多くのペアにもつれを渡し続けることができるのでしょうか?
研究者たちは、この問いを解明すべく具体的な理論モデルを構築して検証しました。
その結果、一見矛盾するようですが、理論上はもつれを分ける量を極めて微量に設定することで、多数のペアにもつれを分け与えることができる可能性が示されました。
ただし実際には、もつれを分け与えるペア数を増やすほど、一つ一つのペアに行き渡るもつれの量が非常に小さくなってしまうため、実用面での限界が出てきます。
それでは、このような理論上の可能性は具体的にどのような仕組みで実現されるのでしょうか?
「量子もつれ」を複数ペアに渡す新技術――理論モデルで検証

研究者たちは、この「量子もつれを次々と渡していく」という新しいアイデアが本当に可能なのかを検証するために、シンプルで直感的な理論モデルを考案しました。
具体的には、まずAさんとBさんという二人の人物がそれぞれ離れた場所にいる状況を設定し、二つの粒子が完全な「量子もつれ」の状態で結ばれているものと想定しました。
この最初の二つの粒子のペアを、もつれの出発点(「源」)と位置づけています。
ここで、別のペアであるCさんとDさんが登場します。
CさんとDさん自身は、もつれた粒子を持っていませんが、もつれを何とかして手に入れる必要があるという状況です。
そこで、CさんはAさんのところへ、DさんはBさんのところへ訪れ、それぞれ粒子を持ち寄ります。
この時、研究者たちが考えたのは、双方の粒子を少しだけ触れ合わせるような特別な操作(これを「結合ユニタリー操作」と呼びます)を行うことです。
結合ユニタリー操作とは、二つの粒子の状態を絡み合わせたり交換したりするために量子力学で使われる基本的な操作のひとつです。
この操作を実行すると、もともと完全な量子もつれ状態にあったA–B間の粒子から一部のもつれが取り出され、新たにもつれた粒子ペアがC–D間に生まれます。
この時点で重要なのは、CさんとDさんはお互いの粒子を直接操作したわけではなく、あくまでAさんとBさんがそれぞれ手元にあった粒子をCさんとDさんの粒子と結びつける操作をしただけ、という点です。
その結果、間接的にCさんとDさんの粒子が新しくもつれ合った状態になるのです。
ただし、この操作をしたことで、最初のA–B間のもつれが完全になくなってしまうわけではありません。
実際には、A–B間にもつれが少し残ることもあり、その「残り」が次のペアに渡すための貴重な資源になります。
これを研究者たちは「もつれのリレー」と表現しています。
では、こうした「もつれのリレー」は一度しか行えないのでしょうか?
研究チームは、このプロセスが繰り返し行える可能性を探りました。
つまり、C–Dペアに操作を行った後も、まだA–B間にもつれが残っているなら、さらに次の新しいペア(E–Fとしましょう)にも同じ操作を繰り返して、もつれを渡していけるかを検討したのです。
その結果、最初に用意したもつれの量が完全になくならない限り、理論的には次々と複数のペアにもつれを渡し続けることが可能であることが示されました。
ここでひとつ重要な疑問が湧いてきます。
理論上は無限に次のペアへと渡し続けられるとしても、それは実際に意味があることでしょうか?
つまり、多くのペアに渡すためには、一回に渡すもつれの量を非常に小さくしなくてはなりません。
そして、一回に渡す量を減らせば減らすほど、多くのペアに渡せますが、各ペアが受け取る量が非常に小さくなってしまいます。
これでは、実際に量子通信や暗号といった現実的な応用には使えないかもしれません。
そこで研究チームは、この「渡す量」と「渡せる人数」の関係を詳しく調べました。
その結果、理論的には、渡すもつれの量を非常に小さくすれば、どこまでも多数のペアに渡すことが可能になる一方で、現実的な下限値(各ペアが最低限これだけのもつれを持っていないと意味がないという値)を設定すると、渡せるペアの数には明確な限界があることがわかりました。
例えば、「各ペアが最低でも2のマイナスx乗(2^{-x})という量のもつれを必要とする」と具体的に決めると、初期のA–B間のもつれ量によって、最大で何ペアまで渡せるかが数学的に決まってしまうのです。
つまり、渡す量を一定以上に保つと渡せるペア数は限られ、逆に多くのペアに渡すためには渡す量が微量になってしまうという「トレードオフの関係」があるのです。
こうした関係を理解するために、研究者たちはあるシンプルな数理モデルを用いてシミュレーションを行いました。
このモデルでは、粒子同士がある種の磁石のような力(スピン相互作用)でお互いに影響し合う状況を仮定しました。
そして、その力の強さや作用する時間を調節して、もつれがどのように移動するかを詳しく観察したのです。
その結果、ある一定の時間まで相互作用させると、もともとA–Bペアが持っていたもつれが完全にゼロになり、そのすべてが新しいC–Dペアへと移動することがわかりました。
これは、もともとあったバケツの水を全て新しいバケツへ移し替えたのと同じ状況です。
ところが、操作する時間を短く調整すれば、A–Bペアのバケツに水を残したまま、一部だけをC–Dペアのバケツへ移すことも可能だったのです。
さらに興味深いことに、相互作用をさらに長く続けると、今度は逆にC–Dペアから元のA–Bペアへともつれが戻る現象も起こりました。
まるでバケツの水が行ったり来たりと揺れ動くように、もつれが「振動」するような状態が観察されたのです。
これは、「もつれ」を局所的な操作で移動させたり再分配したりしても、全体で見るともつれの総量は決して増えないことを示しています。
局所的な操作だけで新しくもつれを生み出すことは量子の基本原理から不可能だからです。
【コラム】「量子もつれの分配」をどう解釈すればいいのか?
量子もつれの分配とは、もともと一対で存在していた量子もつれを、まるで糸を少しずつ引き出して複数のペアに順番にもたらすようなプロセスであることが、今回の研究によって理論的に示されました。この現象を読み解くには鍵となるのが「情報の非局在性」、つまり空間的に離れていても、一度つながった粒子どうしが依然として密接に関連し合うという量子世界の基本特性です。古典物理学的には、遠く離れたものは互いに影響を及ぼさないと考えられますが、量子もつれはそれと真逆の振る舞いをします。これが「非局所性」です。では、分配とは何を意味するのでしょうか。これは単なるコピーや複製ではありません。研究では、一方のペアから部分的にもつれを引き出し、別のペアにゆだねるという操作が理論的に可能であることが示されたのです。すなわち、A–B間のもつれを源とし、C–D間にわずかなもつれを分配する。これを繰り返せば、理論上は多くのペアに非ゼロのもつれを順次分け与えることができます。ただし、全体としてはもつれの総量は増えず、局所操作では新たにもつれを生み出せません。さらに深く見れば、もつれの非局所性は「分離された個物」としての粒子の概念を揺るがします。粒子は離れて存在していても、その状態は決して独立ではなく、全体として「一つ」の情報系として振る舞っているのです。もちろん、この分配によって「高速通信」が可能になるわけではありません。ノーコミュニケーション定理が保証するように、意図的に情報を送受信できるものではないからです。しかし、それでもこの非局所性を使って、量子ビットを複数ユーザーに効率的に分け与える設計は、量子ネットワークや暗号技術の未来的構想に対して大きな示唆を与えます。つまり、「量子もつれの分配」は、非局所的な相関を操作可能な形に応用する、極めて革新的な理論的構想であり、同時に「情報とは空間に依存しない共有可能な資源である」という認識を呼び起こします。
今回の研究を通じて研究者たちは、「少なくとも一組の適切な結合ユニタリー操作を選ぶことで、最初のもつれを完全になくしてしまわない限り、理論的には任意の多数のペアにもつれを順々に渡していける」という結論に達しました。
しかし、現実的に考えれば渡すもつれの量がどんどん微量になり、実用面では限界があることも事実です。
それでは、具体的な操作の仕方やどの程度まで現実的に実用可能かについて、研究者たちはどのように考察しているのでしょうか?
【まとめ】「もつれ分配」の登場で量子通信はどう変わる?
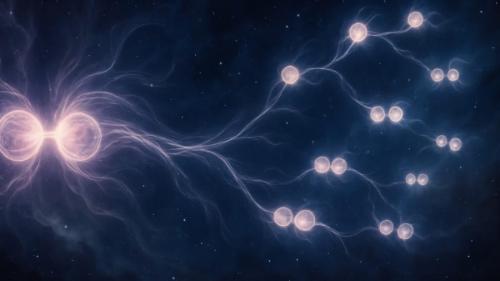
今回の研究によって、量子もつれという一見使い切りと思われていた貴重な資源が、「必要な分だけ取り出して順次分け与えることが可能である」という新しい可能性が示されました。
この結果は、量子もつれをまるで水や電気のような日常的な資源とみなし、柔軟に管理・活用するという画期的な考え方につながります。
これまでは、一度作った量子もつれは二者間で一回使ってしまうと再利用は困難で、量子通信や量子暗号などの実用的な応用を考える上で大きな制約となっていました。
しかし、今回の研究成果が示した「もつれのリレー」というアイデアを応用すれば、限られた量子もつれをより効率的に使い回す道が開けるかもしれません。
例えば、量子通信では離れた地点間でもつれた粒子のペアを配送して利用する必要がありますが、高品質なもつれを遠距離間で作り配送するのは技術的に非常に難しく、高いコストがかかります。
そのため、もし量子通信ネットワークの拠点に一度高品質なもつれペアを準備しておき、それを必要に応じて小出しに分配できれば、通信の効率が格段に向上する可能性があります。
これはまるで銀行の預金口座のように、「量子もつれ」を一箇所に貯蔵しておき、必要になった利用者が順番に引き出して使うという仕組みに例えることもできます。
実際、未来の量子インターネットでは、この「もつれバンク」のような仕組みを使って、数多くの利用者が効率的に通信できる環境が整うことも夢ではないかもしれません。
ただし、この「もつれのリレー」のアイデアにも限界があります。
本研究で示された通り、多くのペアに渡そうとすると、一回あたりに渡せるもつれの量は徐々に小さくなってしまいます。
量子もつれが弱くなりすぎると、それを用いた量子テレポーテーションや量子暗号などの実用的な技術の性能が大きく低下してしまう可能性があるからです。
このため、実際に量子通信や量子暗号を実用化する際には、もつれを分配するペアの数と、それぞれに分け与えるもつれの量を最適に調整する必要があります。
つまり、「どのくらい薄めたもつれまでが実用に耐えるか?」という重要な問いに、今後のさらなる研究が必要になってくるでしょう。
本研究の研究チームも、今回の理論モデルによって量子もつれという貴重な資源をこれまでより効率的に活用できる道が開け、量子技術の発展に大きく寄与する可能性があると期待しています。
また、量子もつれを資源として扱うという考え方は、本研究以外にも近年多様な方向から模索されています。
その一例として「エンタングルメント・バッテリー(もつれの電池)」という別の興味深い理論研究があります。
これは、一度使用すると減少すると考えられていた量子もつれを一時的に保存し、後から再び完全に引き出すことが可能であることを示した研究です。
しかし、どちらも量子もつれをまるで電気や水などの日常的資源のように管理・運用しようという共通した思想を示しています。
ただし、本当に実用化するためには、どのような具体的な方法で粒子を操作し、どのくらいの量のもつれが最低限必要になるのかなど、まだ検証すべき課題が数多く残されています。
それでもこうした研究の積み重ねが、今後さらに進展することによって、量子もつれの柔軟な活用法が生まれ、新しい量子情報技術が現実化していくことも期待されます。
今回の「もつれリレー」の発見は、私たちがまだ完全には理解しきれていない量子力学の不思議さを改めて実感させてくれるものであり、同時に実用的な量子通信や暗号の普及に向けた新たな可能性を示しています。
もしかしたら未来の量子ネットワークは一組の粒子の間に張られた見えない糸から、必要な分だけ糸をほぐして次々と別の人に渡していく仕組みを採用しているかもしれません。
元論文
Local entanglement transfer from an entanglement source to multiple pairs of spatially separated observers
https://doi.org/10.1103/17s4-rtdm
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部
