人間らしさの要素がウイルス由来の遺伝子からも与えられているとしたら、どう思いますか?
人間のゲノムの中には、太古に感染したウイルス由来のDNA断片が数多く潜んでいます。
一昔前までそれらは「ジャンクDNA(がらくたのDNA)」と呼ばれ、特に役割のない遺伝の化石のように考えられてきました。
しかしカナダのマギル大学(McGill University)と日本の京都大学(京大)などによって行われた研究により、古代ウイルス由来のDNA配列が、実は重要な遺伝子スイッチとして人間らしさの進化や人間の健康に影響を与えている可能性が示されました。
例えるなら、ある日会社に侵入して居座ってしまった謎のオジサンが長い年月居座ることでムードメーカーとして溶け込み、やがて会社の仕事を任せられるようにもなり、そして会社の「らしさ」に不可欠な存在になるという話と言えるでしょう。
会社としては最初は厄介でしたが、長い年月を経た現在では、そのオジサンなしには会社らしさを維持できなくなってしまったのです。
マギル大学のギヨーム・ブルク教授は、「人間や霊長類の部分とウイルスの部分とを明確にマッピングできれば、『人間を人間たらしめているもの』が何か、そしてDNAが健康や病気にどう影響しているかを理解する一歩に近づくでしょう」と語っています。
かつて外敵だったウイルスのDNAが、どのようにして人類が人間らしさを獲得することに貢献したのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年7月18日に『Science Advances』にて発表されました。
目次
- DNAの8%はウイルスだった——進化の隠れたシナリオ
- DNAに潜むウイルスが「人間らしさ」を作っていた
- 古代ウイルスが私たちの健康を左右する
DNAの8%はウイルスだった——進化の隠れたシナリオ

私たちの体の中には、祖先から受け継がれた長い歴史が詰まっています。
目の色や髪の毛の質感、身長など、外見に現れる特徴だけではありません。
実はゲノムと呼ばれるDNAの設計図には、驚くべきことに、遥か昔に私たちの祖先に感染したウイルスの痕跡が数多く残されています。
ゲノムの中には「ジャンクDNA」と呼ばれる、役割がはっきりと分からない配列が大量に存在し、その中の少なくとも8%は「内在性レトロウイルス(ERV)」と呼ばれる古代のウイルス由来であることが明らかになっています。
長年、こうしたウイルス由来のDNAはゲノムの中の「ガラクタ」と考えられ、特に重要視されてきませんでした。
しかし、近年になって新たな視点が生まれてきました。
これらのウイルス由来のDNAの一部が、実はゲノムの中で大切な役割を担っているかもしれないことが分かってきたのです。
例えば、哺乳類が胎盤をつくる際に必要な遺伝子を制御するスイッチとして、また幹細胞が体のさまざまな細胞へ変化する際の調整役として、このウイルス由来のDNAが利用されていることが報告されています。
かつては病原体であったウイルスの遺伝子が、長い進化の過程で私たちのゲノムに定着し、新たな役割を与えられているのです。
しかし、研究者にとってこれらのウイルスDNAの研究は決して簡単ではありません。
まず、こうしたウイルス由来のDNA配列は互いによく似ていて、ゲノム中に数百、時には数千という数で散らばっています。
まるで大量の似たようなパズルのピースが混ざった状態で存在しているため、どのピースがどのグループに属しているのかを正確に区別するのが非常に難しいのです。
さらに、これまで使われてきた分類方法は主に配列の類似度だけに基づいており、細かな違いや、実際にどのような機能を持つのかまではうまく分類できていませんでした。
その中でも特に注目されたのが、「MER11」と呼ばれるウイルス由来のDNAグループです。
MER11は比較的新しい時代(数千万年前)に霊長類の先祖のゲノムに入り込んだと考えられている若いグループで、これまでMER11A、MER11B、MER11Cという3種類のサブファミリー(下位分類)に分けられてきました。
ところが、これらの分類は非常におおざっぱで、実際にはもっと細かく分類しなければならないほど、MER11の中には多様な特徴を持つ配列が存在する可能性が示されていました。
また、ヒトゲノムの解析が初めて行われた約25年前に作られた分類法や注釈(アノテーション)自体も、すでに古くなってしまっていることが指摘されていました。
そこで今回の研究チームは、このようなウイルス由来のDNA配列が「本当はどのような系統に分かれていて、どのような特徴や役割を持っているのか」を改めて調べることにしました。
日本の京都大学やカナダのマギル大学など、複数の国際的な研究機関が協力し、このMER11というウイルス由来の配列の正体を、進化の系統に基づいて徹底的に洗い直すことに取り組んだのです。
果たして、この古代のウイルスが私たちのゲノムに潜ませた謎のDNAは、現代の私たちにどのような影響を与えているのでしょうか?
そして、それらのDNA配列はどのようにして遺伝子を制御し、人間らしさに貢献しているのでしょうか?
DNAに潜むウイルスが「人間らしさ」を作っていた

古代のウイルスが私たちのゲノムに潜ませた謎のDNAは、現代の私たちにどのような影響を与えているのでしょうか?
これらのDNA配列は、具体的にどのように遺伝子を制御し、私たちが人間らしさを獲得する上でどんな役割を担っているのでしょうか?
こうした謎を解明するため、研究者たちはまず、ゲノムに散らばった膨大なウイルス由来のDNA断片を「正しく分類する方法」から見直すことにしました。
これまでの研究では、ウイルスDNAの分類は主に配列の類似度だけを基準にして行われていましたが、この方法ではDNA断片の微妙な違いや本来の関係性を見逃す恐れがありました。
そこで研究チームは、従来のやり方を根本的に見直し、進化的な系統関係(どのDNA断片がどの断片から派生したかという関係性)や、それぞれの断片が霊長類の種間でどれほど保存されているのか、という視点を取り入れた新しい手法を開発したのです。
具体的には、ヒトや霊長類のゲノムに含まれるMER11というウイルス由来のDNA配列に着目しました。
先にも述べたようにこのMER11は、比較的新しい時代(数千万年前)に霊長類の祖先のゲノムに入り込み、その後数千という単位でコピーを増やしていったもので、これまでMER11A・MER11B・MER11Cの3つのグループ(サブファミリー)に分類されていました。
しかし、新しい系統分類の方法を使って詳しく調べてみると、MER11は実はもっと細かな分類に分けられることが分かりました。
従来の3つのグループは再整理され、新たにMER11_G1、MER11_G2、MER11_G3、MER11_G4という4つのグループに分類されたのです。
この結果、それまでの分類法では約20%近く(正確には19.8%、412個)の配列が間違ったグループに入れられていたことが明らかになりました。
この新しい分類方法により、それぞれのMER11グループが、ゲノム内でどの染色体のどの領域に分布しているのかという特徴もより正確に理解できるようになりました。
さらに、それぞれの新しいグループには、DNAの化学修飾や転写因子の結合パターンといった、遺伝子がオンやオフになる際に重要な「エピジェネティックな特徴」にもはっきりとした違いが認められました。
つまり、この新分類法は単に分類を正確にしただけでなく、DNA配列が持つ機能的な性質の違いまで明確に浮かび上がらせることに成功したのです。
しかし、新しい分類が実際に意味を持つのか、つまりMER11のDNA配列が本当に遺伝子のスイッチ(エンハンサー)として働くのかを確かめなければなりません。
この答えを得るため研究者たちは、「レンチウイルスを用いた多数並列レポーターアッセイ(lentiMPRA)」という新しい実験手法を使うことにしました。
この方法は、調べたい何千種類ものDNA配列をそれぞれレポーター遺伝子に連結して細胞に導入し、それぞれの配列がどのくらい遺伝子の活動を高めるのかを一度に測定できるものです。
具体的には、ヒトのiPS細胞(体の様々な細胞に変化できる能力を持つ細胞)と、そこから分化した初期の神経細胞に、MER11由来の約7,000種類のDNA配列を導入しました。
すると、特にMER11_G4という新しいグループの配列が、他のグループと比べて非常に強力な遺伝子活性化能力(エンハンサー活性)を示すことが明らかになりました。
このことは、MER11_G4が、ヒトの発生の初期段階で重要な役割を果たす可能性を強く示しています。
さらに詳しく調べると、MER11_G4の配列には、他のグループには存在しない特徴的な「モチーフ」と呼ばれる特定の配列パターンがありました。
このモチーフは、転写因子(遺伝子をオンにするタンパク質)が結合する目印として機能し、どの転写因子が結合するかによって、そのDNA配列が働く場所やタイミングが決まります。
研究者たちは、このMER11_G4のモチーフが、ヒトやチンパンジーのような大型類人猿には存在するものの、それより下位のサル(例えばマカク)には見られないことを発見しました。
さらにその違いは、たった1つのDNA塩基が欠失するというごく小さな変異によって生まれたことも突き止めました。
つまり、このたった一つの変異が、新しい遺伝子スイッチを生み出し、ヒトやチンパンジーの発生において重要な役割を担う可能性が出てきたのです。
こうした発見から、古代のウイルス由来DNAが、現代の私たちのゲノムの中で実際に新しい調節機能を獲得し、霊長類種間の違いを生み出す「進化の実験場」となっている可能性が見えてきました。
今回の研究ではMER11を中心に調べましたが、研究チームはこの方法を他のウイルス由来配列にも応用しました。
その結果、他にも本手法を53のシミアン特異的 LTR サブファミリーに適用した結果、26サブファミリー中のインスタンス約30%(3807件)が新たに注釈付けされ、合計75の新サブファミリーが提案されました。
これは、私たちのゲノムに隠されている調節配列をより正確に見つけ出し、人間の特性や疾患の謎を解く新しい道を拓くかもしれません。
古代ウイルスが私たちの健康を左右する
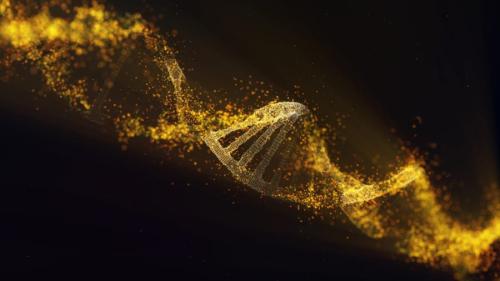
今回の研究結果から、私たちの体の中に眠っていた「ジャンクDNA」と呼ばれる不思議な領域に対する見方が大きく変わりました。
これまで「ジャンクDNA」という名前からも分かるように、このDNA領域は「役に立たない無意味な遺伝子のガラクタ」として軽視されてきました。
しかし、実際はこの領域に、驚くほど重要な役割が隠されていたのです。
しかもその役割は、人間の進化や赤ちゃんが母親の体内で育つ過程、さらには病気にさえ影響を与えるほど広範囲なものでした。
元をたどれば、これは数千万年も昔に私たちの祖先がウイルスに感染したことに端を発しています。
本来、ウイルスは外敵であり感染した生物に悪影響を与える存在です。しかし、進化の長い歴史の中で、このウイルスのDNA断片は私たちの祖先のゲノムの中に入り込み、そのまま次の世代へと受け継がれてきました。
初めは単なる「DNAの中のノイズ」のような存在だったかもしれませんが、徐々に宿主である私たちのゲノムに取り込まれ、いつの間にかゲノム全体を調節する大切なスイッチ役として働くようになっていたのです。
こう考えると、まるでかつての侵入者であるウイルスが、今やゲノムの重要な「管理者」として私たちの生命を支えているような不思議さを感じるかもしれません。
今回の研究がもたらした最大の意義は、私たちが長年見過ごしてきた「ジャンクDNA」や「ゲノムの暗黒物質」と呼ばれる領域の中にこそ、ゲノムの機能や進化の謎を解く鍵が潜んでいることを明確に示した点にあります。
例えば最近の研究では、これまで無視されていたジャンクDNAの配列を詳しく調べることで、がんの早期発見や珍しい病気の診断に役立つ新しい方法が開発されています。
ある研究では、血液中のDNAに含まれるジャンクDNA配列の活動パターンを人工知能で解析し、高精度でがんを検出する方法が報告されています。
また別の研究では、これまで原因が全く分からなかった難病の患者のゲノムを、タンパク質を作る遺伝子以外の領域まで徹底的に調べ直した結果、まさにジャンクDNAと呼ばれた部分にあった小さな変異が病気の原因だったことを発見し、患者の治療を大きく前進させる成果を上げています。
これらの例からも、ジャンクDNAが持つ可能性がどれほど大きいかがわかります。
ヒトゲノムが最初に解読された約25年前、人類は「ゲノムの全てが明らかになった」と感じたかもしれません。
しかし実際には、私たちはゲノムの設計図のほんの一部しか理解できていなかったのです。研究チームの中心人物の一人である京都大学の井上博士も、「私たちのゲノム配列は既に全て読み取られていますが、その大部分の機能は未だに不明なままです。
特にトランスポゾンやウイルス由来の配列は、ゲノムの進化や私たちの生命活動に重要な役割を果たしている可能性があり、研究が進めば進むほど、その重要性が明らかになっていくでしょう」と話しています。
実際、今回の研究で中心的役割を担ったMER11というウイルス由来配列を詳しく解析したところ、人間やチンパンジーなど大型類人猿の系統に特有の遺伝子調節スイッチが存在することが明らかになりました。
これは「私たちが人間らしくあるために必要なDNAの断片」が、かつてのウイルスの痕跡に由来している可能性を強く示しています。
この点についてマギル大学のギヨーム・ブルク教授は、「もし私たちのゲノムの中にある、人間や霊長類に特有な部分とウイルスに由来する部分をはっきりと区別できれば、私たちが『なぜ人間なのか』という根本的な問いに対する答えに近づくことができるでしょう。さらにDNAが健康や病気にどう影響するのかも、これまで以上に詳しく理解できるようになるでしょう」と強調しています。
今回の研究成果は、人類がゲノムという巨大な設計図を理解する新しい時代の幕開けとなるかもしれません。
これまで私たちが単なる「余白」と考えていた領域に新たな意味を見出すことで、「生命とは何か」、「人間とは何か」という私たちが抱く根源的な疑問に迫る、壮大な旅がはじまるのかもしれません。
元論文
A phylogenetic approach uncovers cryptic endogenous retrovirus subfamilies in the primate lineage
https://doi.org/10.1126/sciadv.ads9164
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部
