三人姉妹は8分の1ではありませんでした。
アメリカのハーバード大学で行われた研究により、赤ちゃんの性別は家庭(母親)ごとに一定の傾向(偏り)が存在することが明らかになりました。
研究チームは、約5万8千人の母親とその子供14万6千人以上のデータを分析したところ、3人続けて男の子を産んだ母親は4人目も男の子を産む確率が61%、3人連続女の子だった場合も4人目が女の子になる確率は58%と、いずれも60%前後であり偶然(50%)を大きく超えていました。
これは各家庭(母親)ごとに男児または女児が生まれやすい確率が偏る「重り付きのコイントス」が行われているようなものだと研究者らは述べています。
また、母親の初産年齢が高い場合や特定の遺伝的変異(NSUN6、TSHZ1)を持つ場合に、同じ性別ばかりが生まれる可能性が有意に高くなることも判明しました。
いったい何がこうした家庭ごとの性別偏りを引き起こしているのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年7月18日に『Science Advances』にて発表されました。
目次
- なぜ一部の家庭では男の子ばかり・女の子ばかりなのか?
- 3人の子どもが同じ性別であれば4人目も同じ性別が生まれる確率は約60%
- 母親の遺伝子に隠された「男児優勢・女児優先」スイッチとは
なぜ一部の家庭では男の子ばかり・女の子ばかりなのか?

「うちの家系は男の子ばかり」「うちは姉妹だけ」という話は、誰しも一度は耳にしたことがあるでしょう。
親戚や友達を見渡すと、性別が極端に偏った兄弟姉妹を持つ家庭は決して珍しくありません。
「たまたま偶然が続いただけ」と考える人もいますが、実は昔から「何か科学的な理由があるのではないか?」という疑問が議論されてきました。
そもそも、生物学の教科書では「赤ちゃんの性別は父親の精子によって決まる」と説明されています。
精子には性別を決定する染色体が入っており、それはX染色体かY染色体のどちらかです。
精子はこのXとYを半々の確率で含むため、男女が生まれる確率は各妊娠ごとに常に50%だと考えられてきました。
例えるなら、完全に公平なコイントスを毎回しているようなものです。
しかし現実には、なぜか性別が偏っている家庭が多く見られるのです。
その理由を説明するために、これまで科学者たちはさまざまな説を唱えてきました。
例えば、
「美男美女のカップルからは女の子が多く生まれやすい」
「背が高く経済的に豊かな夫婦には男の子が多い」
といった、親の特徴に注目した興味深い説があります。
【コラム】美男美女や豊かさは子供の性別に関係するのか?
「美男美女のカップルからは女の子が生まれやすい」「背が高く経済的に豊かな夫婦には男の子が多い」という仮説は全くのデタラメかと言えば、一応生物学的な根拠に基づいた仮説となっています。その根拠とは「生物は状況に応じて、子孫を残しやすい性別(オスまたはメス)を産み分ける傾向が進化している可能性がある。」というものです。
具体的に言えば美男美女のカップルが女の子を産みやすいという説は、「女性の美しさは男性に比べてより強く繁殖成功に直結する」と考えられるため、美しい両親は自分の魅力的な遺伝子を効果的に次世代に伝えるために女児を多く産むよう進化しているかもしれない、という仮説に基づいています。一方、背が高く経済的に豊かな夫婦が男の子を産みやすいという説は、社会的地位や経済力が繁殖成功により大きなメリットを与える男性に有利であり、親がその優位性を次世代に引き継ぐために男児を産む傾向を進化させた可能性がある、という考えに基づいています。ただこれらの説は、一見合理的なように思えますが、あくまで進化生物学における理論的仮説の段階であり、人間において裏付けがあるわけではありません。
また、生物学的に「受精時の母体の環境が性別を左右する」という説も長年議論されています。
これは、受精の瞬間に母親の体内環境(例えば膣内の酸性度や体温、排卵のタイミング)が影響して、X染色体かY染色体のどちらかを持つ精子の受精率が変化するという考え方です。
しかし、こうした説は一見もっともらしく聞こえますが、大規模なデータ分析や疫学調査で明確に裏付けられたことはありませんでした。
また、出生時の性別に関係する遺伝的要因についても、十分な研究は行われていませんでした。
そこで今回、ハーバード大学の研究チームは大規模なデータを活用し、この「家庭ごとの性別の偏り」の真相に本格的に挑むことにしたのです。
果たして、性別の偏りは本当に単なる偶然に過ぎないのか、それとも何か科学的な根拠があるのか——?
そして、もし科学的な理由があるとすれば、それはいったいどのようなメカニズムで起きているのでしょうか?
3人の子どもが同じ性別であれば4人目も同じ性別が生まれる確率は約60%
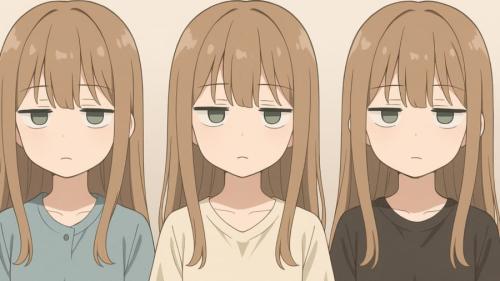
カップルや母体の条件によって、生まれやすい性別があるのか?
この謎を解明するために、研究者たちは分析の単位を個々の出産から各母親に切り替えました。
従来の研究の多くは出生ごとにデータを集計し、性別とさまざまな要因との関連を探していました。
しかし、それでは家族内に存在するかもしれない性別の偏りパターンが見逃されてしまう可能性があります。
そこで研究チームは、家族(母親)ごとに見たときに、子どもの性別が本当に公平なコイントス的な確率分布に従うのか、それとも母親ごとに偏り(ばらつき)があるのかを検証することにしました。
さらに、もし偏りがあるとすれば、どのような要因が「男の子ばかり」や「女の子ばかり」をもたらすのか(例えば遺伝的な体質なのか、母親の年齢などの属性なのか)を探ることにしました。
調査にあたってはまず、各母親について子どもたちの性別の並びを分析し、その分布を「期待されるランダム分布」と比較しました。
その結果、子どもの人数(きょうだいの数)が多い家庭ほど、性別の分布が単純な50%の期待値からズレていることが明らかになりました。
言い換えれば、家族内で子どもの性別が偏って生まれているケースが、偶然では説明できないほど多く存在するのです。
統計的には、この分布は従来考えられていた単純な二項分布(各出生が独立で50%の確率)ではなく、各家庭ごとに確率が異なる「ベータ二項分布」に適合すると分析されました。
これはまるで「各家庭ごとに重りのついた(偏った)コインを投げているようなもの」だと研究者らは表現しています。
ある母親はやや男の子が生まれやすいコイン、別の母親は女の子が出やすいコインを持っている、といったイメージです。
この偏りを端的に示すため、研究では「次の子が同じ性別となる条件付き確率」を計算しました。
モデルによれば、最初の2人が同じ性別だった家庭では、3人目も同じ性になる確率が約54%程度と、やや50%を上回りました(男児2人の場合は3人目も男児、女児2人の場合は3人目も女児)。
さらに、3人連続で同じ性別だった家庭では、その確率が一層高くなり、男児が3人続いた家庭では4人目も約61%、女児が3人続いた家庭では4人目も約58%という予測が得られました。
実際のデータでも、4人目以降までいる家庭数は限られるものの、概ね同様の傾向が確認されました。
この結果は、「一度出たコインの目に次もなりやすい」という家族内相関の存在を示唆しています。
一方で、データには「親の意思による子どもの人数調整」も反映されています。
例えば「男の子と女の子を一人ずつ得たらそれ以上子どもはもう十分」と考えて、2人で打ち止めにする夫婦も多いでしょう。
実際、本研究でも2人きょうだいの家庭では「1人が男児、もう1人が女児」というパターンが他の組み合わせ(男男・女女)より有意に多いことが確認されました。
これは男女が揃った時点で出産をやめるカップルが多いことを反映したものと考えられます。
反対に、3人以上のきょうだいがいる家庭では同性ばかりの組み合わせが混合より増える傾向が見られました。
つまり「同じ性別の子が続いたので、違う性の子を求めてもう一人トライした」というケースもあれば、それでも結果的に同性が続いてしまった家族も多いわけです。
このように親の行動(望む性別の子どもができるまで産み続ける/両性が揃ったらやめる)は、家族内の性別パターンに影響を与えます。
この影響を取り除いて純粋な生物学的傾向を測るため、研究チームは各女性の「最後の出産」を除外する感度分析も行いました。
すなわち、各家庭がもう一人子どもを持つと仮定して分析することで、「打ち止め効果」(いわゆる“コレクター趣向”)を弱めたのです。
その結果、偏りの傾向はむしろ一層鮮明になり、統計的な有意性も高まったといいます。
これは、親の出産打ち切り行動が偏り現象を過小評価させていた可能性を示しています。
つまり、本来はもっと偏りやすい体質の母親であっても、途中で出産をやめてしまえば「偶然両方産んだだけ」のように見えてしまうからです。
このように、子どもの性別が家庭ごとに異なる『偏り』を持つことが、統計的にも明確になりました。
しかしそうだとすると、いったい何が母親ごとに生まれやすい性別を決めているのでしょうか?
母親の遺伝子に隠された「男児優勢・女児優先」スイッチとは

では、なぜ母親ごとに子どもの性別の偏りが生じるのでしょうか。
研究チームはこの問いに迫るため、考え得る様々な母親側の要因をデータから検証しました。
年齢、人種、体格、生活習慣、さらにはゲノム解析(遺伝子レベルの差異)まで網羅的に調べたのです。
その結果、いくつかの興味深い関連要因が浮かび上がりました。
まず明らかになったのは母親の年齢の影響です。
特に初産(最初の子を産んだ時)の年齢が高い女性ほど、その後子どもの性別が一方に揃う傾向が強いことが分かりました。
統計的には、初産年齢が29歳以上のグループは22歳以下のグループに比べて、「子どもが全員同じ性別になるオッズ」が約1.13倍(95% CI: 1.04–1.24)と報告されています。
わずか一割強の差ではありますが、人口レベルで見れば意味のある偏りです。
一方、身長については1インチ(約2.54cm)高くなるごとに「子どもが全員同じ性別になるオッズ」が約13%減少する(OR=0.87, P=0.004)という統計的に有意な傾向が見られました。
それ以外の要因、人種(白人か否か)、若い頃のBMI(体格)、血液型、生活リズム(朝型か夜型か)などには有意な関連は認められませんでした。
このように、際立った要因は「母親の年齢」と「身長」でした。
もう一つの重要な手がかりは遺伝的要因でした。
研究チームは一部の参加者から得られた遺伝子データを用い、ゲノムワイド関連解析(GWAS)によって「全ての子が同じ性別であること」に関連する母親側の遺伝子変異を探索しました。
その結果、2つの遺伝子領域が統計学的に有意な関連を示しました。
一つは第10番染色体上の「NSUN6」という遺伝子に存在する変異で、この変異を持つ母親は娘(女児)のみを産む傾向があることが示唆されました。
もう一つは第18番染色体上の「TSHZ1(Teashirt Zinc Finger Homeobox 1、ティーエスエイチゼットワン)」という遺伝子の近傍の変異で、こちらを持つ母親は息子(男児)のみを産む傾向が示されました。
これらの遺伝子はこれまで性別や生殖に関与すると知られておらず、今回の発見は新しいメカニズムの存在を示唆しています。
以上の結果を踏まえ、研究チームは子どもの性別の偏りが生まれる理由として複合的な要因を指摘しています。
それらを大きく分けると二つになります。
一つ目は生物学的要因です。
例えば加齢に伴って月経周期の卵胞期が短縮するとY染色体精子が有利になる可能性(男児が生まれやすい)や、膣内環境が酸性に傾くとX染色体精子が有利になる可能性(女児が生まれやすい)が指摘されていますが、これらはまだ仮説段階です。
各女性が年齢とともに示すこうした変化の度合いが異なるために、結果として「この人は男の子ばかり」「この人は女の子ばかり」という差が生じうる、と研究者らは推測しています。
また、遺伝子変異の関与についても、ホルモン分泌の微妙な違いや受精卵の着床・維持能力、あるいは夫婦の相性(免疫学的適合性)などを介して性別に偏りをもたらす仕組みが存在する可能性があります。
今回検出された遺伝子変異は、母親の初産年齢や他の生殖関連形質(初経や閉経の年齢など)とは無関係に作用していると考えられ、今後その具体的な働きを突き止めることで新たな生命科学的知見が得られるでしょう。
二つ目は行動学的要因です。
親が望む性別の子どもを得るまで子作りを続ける、あるいは男女両方を得た時点で子作りをやめるといった家族計画上の意思決定も、家族内の性別パターンに影響を与えます。
特に先述のように2人までの子どもでは「男女1人ずつ」で打ち止めとなる夫婦が多いため、全体として男女が揃った家庭が過剰に多く見えます。
一方、もともと生物学的に偏りやすい母親であっても、希望の異性の子どもを得るため通常より多く出産するケースが考えられます。
研究チームは、このような人間の行動要因と生物学的要因の両方が相互に作用しあって実際のデータに現れる偏りを形作っている可能性が高いと結論付けています。
たとえば、生物学的に「男の子ばかり生まれやすい母親」ほど女の子を求めて出産回数を増やす傾向があり、その結果として非常に子沢山になるも結局全員男の子……という家族も想定されます。
このような場合、生物学的な偏りに行動上の偏り(性別に影響された出産行動)が拍車をかけ、統計的に見た偏り現象を一層際立たせているかもしれません。
今回の研究は、「赤ちゃんの性別は基本50/50」という従来の常識に一石を投じる発見と言えます。
もちろん、「3人男の子が続いたから次も必ず男の子」という絶対的な決定論ではありません。
上記の通り確率はせいぜい60%程度であり、依然かなりの部分は偶然に左右されることも事実です。
しかし、「次こそ女の子が欲しいからもう一人…」と考える場合に「その確率は半々より低いかもしれない」という視点は、家族計画を考える上で知っておいて損はないでしょう。
オックスフォード大学の人口統計学者ジョシュア・ワイルド(Joshua Wilde)氏は、「子どもの性別が続いている家族には次の子も同じ性別になる可能性が少し高まることを伝える必要があるかもしれない」とコメントしています。
実際、今回明らかになった母親ごとの性別の偏りは、科学的にも興味深いだけでなく、将来的には産科医療やカウンセリングの現場で両親の心構えに影響を与える可能性があります。
元論文
Is sex at birth a biological coin toss? Insights from a longitudinal and GWAS analysis
https://doi.org/10.1126/sciadv.adu7402
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部
